HARMONYNEWS 丂1998 廐
僴乕儌僯乕丒僀儞僞乕僫僔儑僫儖丒僯儏乕僗儗僞乕 No.19
丂
抝偲彈偺垽偺偐偨偪
僶儔儖 攷巕
俫俬俠夛堳
恖惗傪婫愡偵椺偊偰拞崙恖偼惵弔丄庨壞丄敀廐偦偟偰尯搤偲尵偆丅"抝偲彈偺垽偺宍"偲偄偆崱擭偺僯儏乕僗儗僞乕偺戣偼丄偄偐偵傕庨壞偺彈払偑懡偄僴乕儌僯乕偵傆偝傢偟偄丅巹偼偝偟偢傔敀廐偐傜尯搤偺婫愡偵懏偡傞偙偲偱偁傝丄堦恖偺抝偲31擭傕傂偨偡傜楢傟揧偭偰偒偨彈偱傕偁傞丅嬤擭偄偝偝偐変乆晇晈傕屚傟偰偒偨傛偆偱丄崱傗垽偺宍偼"摨巙垽"偵嬤偄傛偆偵巚偆丅偙傟偱偼愘暥傪撉傫偱偔偩偝傞曽乆偵偼偄偐偵傕戅孅備偊丄尰嵼巹偺傑傢傝偱嵟傕儂僢僩側抝偲彈偺榖偐傜巒傔傛偆丅
偙偺抝40嵥丄変乆晇晈偑嵟傕偦偺彨棃偵婜懸傪偐偗偰偄偨桪廏側傞僄儞僕僯傾丄恀柺栚偱摥偒幰丄7嵥擭忋偱偼偁傞偑尗偄彈偲斵偼20嵥偱寢崶丄偐傢偄偄彈偺巕偑傆偨傝偄偰峹奜偵堏傝廧傫偱18擭丄奊偵昤偄偨傛偆側岾暉側壠掚傪塩傫偱偄偨丅斵偺寚揰偲尵偊偽捈忣宎峴宆偱偁傞偙偲丄攚傕崅偔僴儞僒儉偱偁傞偙偲丄側偤僴儞僒儉偑傛偔側偄偐偱偡偭偰丠彈偨偪偵儌僥傑偡傢偹乮僋儕儞僩儞巵偺斶寑偺椺傕偁傞偠傖側偄偱偡偐乯丅
夛幮偺弌挘偱娯崙偵峴偭偨帪丄嵟弶偺2儢寧偼壠懓偑楒偟偔偰傗偣悐偊傞傎偳偩偭偨斵偑丄尰抧偺彈偺巕偲楒偵棊偪偨偲偄偆僯儏乕僗偑揱傢偭偰棃偨帪偼扤傕怣偠傞偙偲偑偱偒側偐偭偨丅傗偑偰婣偭偰偒偨斵偺曄杄傇傝偵扱偒斶偟傓嵢偵丄斵偼尵偭偨丅
乽斵彈偲偺偙偲偼偗偭偟偰堦帪偺晜婥偱偼側偄丄斵彈偵夛偭偰恖惗偺壙抣娤偑曄傢偭偰偟傑偭偨偺偩丄彏偄偼昁偢偡傞丄怽偟栿側偄偑帺桼偵偟偰傎偟偄乿
偲丄僗乕僣働乕僗傪傂偲偮帩偭偰弌偰峴偭偰偟傑偭偨丅偙偺抝偼偦偺屻偳傟傎偳恖偵旑傝傪庴偗傛偆偑丄旕擄偝傟傛偆偑丄傂偨偡傜垽恖偵偍傏傟偰丄偁傑傝捛偄媗傔傞偲壗傪偡傞偐暘偐傜側偄偲偄偭偨忬懺偵側偭偨丅偦偺彈傕庲嫵偺嫵偊偑傑偩傑偩尩偟偔巆偭偰偄傞娯崙偺抧曽弌恎偵傕偐偐傢傜偢丄恊傕崙傕幪偰僇僫僟傊弌偰棃偰偟傑偭偨丅
偦傟偐傜2擭丄傑偩斵偺棧崶偑惉棫偟偰偄側偄偗傟偳丄崱偙偺傆偨傝偼彫偝側傾僷乕僩偱曅帪傕棧傟傜傟側偄偲偄偆傛偆側枿寧偺帪傪夁偛偟偰偄傞傛偆偩丅偟偐偟丄偙偺傆偨傝偑偨偲偊柍帠偵寢崶偟偰傕丄壗擭傕偟側偄偆偪偵丄抝偼棤愗偭偨嵢傗巕嫙偨偪傊偺孳嵾傪峫偊擸傓傛偆偵側傞偩傠偆偟丄彈偵傕亀偁傟傎偳寜偔嵢巕傪幪偰偨抝偩傕偺丄巹傕偄偮偐偼幪偰傜傟側偄偐偟傜亁偲晄埨偑傛偓傞偺偱偼側偄偩傠偆偐丅棁偱壠傪弌偰丄慡偰偺廂擖偺敿暘偼嵢巕傪梴偆偨傔偵梕幫側偔庢傜傟偰偄偔丅帺嬈帺摼偲偼偄偊丄昻偟偝傕偙偺傆偨傝偺偙偙傠傪偄偮偟偐怚傫偱偄偔偺偱偼側偄偩傠偆偐丅嬛抐偺栘偺幚偼娒偄偑備偊偵丄偦偺屻偵巆傞嬯偝傕傑偨奿暿偺傕偺偩傠偆丅
恖條偩偗傪樧忋偵忔偣偰偼婥偑傂偗傞偺偱丄抪傪擡傫偱巹偺帠傕彂偄偰傒傛偆丅傑偩20戙偺偙傠乮墦偄愄偺偙偲両乯偙偺恖偺偨傔側傜柦傕惿偟偔側偄偲巚偄媗傔偰偄偨擔乆偑偁偭偨丅偦傟傑偱偵傕恖傪岲偒偵側偭偨偙偲偼偁偭偨偺偵丄斵偵夛偭偰弶傔偰恖惗傪惗偒偨偲偄偆姶妎傪傕偭偨偺偩偭偨丅
巄偔偺娒偄柌傕丄斵偺怱曄傢傝偵婥偑晅偄偨帪偐傜丄巹偵偼抧崠偺嬯偟傒偑巒傑偭偨丅偦偺搟摀偺偛偲偔峳傟嫸偆巚偄偼丄恖奿傕棟惈傕幮夛偺潀偝偊傕墴偟棳偡傎偳嫮偄傕偺偱偁偭偨丅抝偑巹偺抦恖偲奜崙偱寢崶偡傞偲偄偆寛掕揑棤愗傝傪偟偨偙偲偱廔傢傜側偗傟偽丄巹偼娫堘偄側偔帺柵偟偨偩傠偆丅偟偐偟挿偄挿偄擭寧傪宱偰丄崱偵偟偰巚偊偽庒偄擔偵擬偄墛偵恎傪庈偄偨妎偊偑偁傞偐傜偙偦丄巹偺傛偆偵堏傝婥偱寖偟偄惈奿偺恖娫偵偟偰偼亀寢崶亁偲偄偆惷偐側垽偺宍傪戝愗偵偟偰偄傞偺偐傕偟傟側偄丅
垽偑晄栄偺帪戙丄垽偲偄偆傕偺偑崿撟偲偟偰偄傞偺偑崱偺悽偺拞偩偲巚偆丅擔杮偱幮夛尰徾偵傑偱側偭偨偲偄偆"幐妝墍"乮偦偺偳偓偮偄撪梕偵偼傊偒偊偒偟偨偑乯丄偮傑傞偲偙傠垽偼怱拞偲偄偆宍偱偟偐姰寢偟偊側偄丄偲偄偆嶌幰偺巚憐偵恖乆偼偳偙偐偱擺摼偡傞傕偺偑偁偭偨偺偩傠偆丅傑偨壗搙傕娤偨偲尵偆恖偑偄傞"僞僀僞僯僢僋"乮巹偱偝偊3搙傕娤偨乯丄崱悽婭嵟崅偲偄傢傟傞僴僀僥僋傪嬱巊偟偨偦偺戝妡偐傝側嶌昳偵傕嬃偄偨偗傟偳丄庡墘偺僨僇僾儕僆偑暞偡傞僕儍僢僋偑丄儘乕僘傪巰傪搎偗偰媬偆偦偺弮垽偵丄恖乆偼怱懪偨傟偰椳偟偨偺偩偲巚偆丅
僆僩僐偲僆儞僫偺垽偺宍偵偮偄偰偺掕媊偼丄恖偦傟偧傟偵堘偆偲巚偆丅偟偐偟恖偼垽偝偢偵惗偒偰偄偗側偄丅偦傟備偊偵垽偼恖乆偑塱墦偵捛媮偡傞僥乕儅偱偁傝懕偗傞偺偩傠偆丅
丂
亀擔杮恖偺垽偲巰亁亅 怱拞峫
晍巤 朙惓
儓乕僋戝妛柤梍嫵庼亅帺嶦妛
擔杮恖偺帺嶦偺摿挜偺堦偮偵怱拞偑偁傞丅暋悢帺嶦偲偟偰偺怱拞偼丄戝暿偟偰忣巰偲堦壠怱拞乮偦傟偼峏偵晝巕怱拞丄曣巕怱拞偵暘椶偝傟丄師偵崌堄偐柍棟怱拞偐偱暿偗傜傟傞乯偵傢偗傜傟傞丅忣巰偼垽恖乮堎惈傑偨偼摨惈乯傪娷傓帺嶦偱偁傞偑丄擔杮偺暥壔巎傪捠偟偰奒媺惂搙偲恖娫娭學偑尩偟偔婯掕偝傟偰偄偨摽愳帪戙偵懡偔尒傜傟偨丅摉帪偺嬤徏栧嵍塹栧偺160偵嬤偄媃嬋偼丄楌巎揑儘儅儞偲媊棟恖忣偺棈傒崌偭偨斶寑偵戝暿偝傟傞偑丄斶寑偺懡偔偼怱拞暔偱偁偭偨丅斵偺斶寑偵搊応偡傞恖暔偼摽愳帪戙偺偁傜備傞幮夛奒憌偺抝彈傪娷傒丄媊棟恖忣偲偒傃偟偄幮夛偺潀偲偺斅偽偝傒偵側偭偰帺嶦偟偰備偔暔岅偑杦偳偱偁傞丅乽慭崻嶈怱拞乿乮1702擭乯丄乽怱拞揤偺栐搰乿乮1720擭乯側偳偼丄偙偺擔杮揑側乽斅偽偝傒偺僕儗儞儅乿傪幚偵椙偔昤幨偟偰偄傞丅
慠偟丄偙偺傛偆側崌堄怱拞乮忣巰乯偼丄晻寶幮夛偺潀傗姷廗偐傜夝曻偝傟偨偼偢偺愴屻偺擔杮偱傕尒傜傟傞偺偱偁傞丅晉巑嶳榌偺庽奀偱偙偺悽偱寢偽傟側偄垽傪棃悽偱寢傏偆偲偡傞怱拞乮忣巰乯偑崱傕偭偰屻傪偨偨側偄丅偩偐傜崱偱傕帪乆寈嶡偲帺塹戉偺嫟摨憑嶕戉偑晉巑嶳榌偺偆偭偦偆偲偟偨庽奀傪偐偒傢偗丄怱拞偟偨恖乆偺巰懱傪廂梕偟偰偄傞丅巹帺恎丄晉巑嶳榌偺嬤偔偺堛壢戝妛偱帺嶦妛偺島墘傪偟偨偁偲丄悢恖偺惛恄壢堛偺埬撪偱偦偺庽奀偺拞傪尒妛偝偣偰傕傜偭偨帠偑偁傞偑丄墱怺偔擖傞憑嶕戉堳払偼丄巰恖偺崶楃偺惏拝傪尒偰丄偙偺悽偱壥偨偟摼偸垽偺宊傝傪偁偺悽偱壥偨偦偆偲偟偨抝彈偺堚懱偵椳傪桿傢傟傞偲偄偆丅
垽恖丄壠懓偺摨堄傪摼偰偺帺嶦偑崌堄怱拞偱偁傝丄摨堄側偟偵憡庤傪愭偵嶦偟丄偦偺捈屻帺嶦偡傞偺偑柍棟怱拞偱偁傞丅偩偐傜柍棟怱拞偼懠嶦偲帺嶦偺暋崌宆偱丄擔杮偺傒側傜偢奜崙偵傕尒傜傟傞丅杒暷偱偼丄帺暘傪棧傟偰備偔嵢傗垽恖傪嶦偟丄偦偺捈屻帺嶦偡傞偲偄偆抝惈偵傛傞柍棟怱拞偑傛偔尒傜傟傞丅偦傟偵懳偟偰丄擔杮恖偵傛偔尒傜傟傞偺偼曣恊乮偦偟偰嵢乯偵傛傞柍棟怱拞偱偁傞丅曣惈幮夛偲偄傢傟傞擔杮偺堦壠怱拞偺80亾埲忋偑曣巕怱拞偱偁傞偲偄偆帠幚偼拲栚偵抣偟丄怱拞偲偄偆旤壔偝傟偨尵梩傛傝傕乽巕嶦偟帺嶦乿偲偼偭偒傝尵偆傋偒偱偁傠偆丅
曣巕怱拞偼晇偑晄嵼拞偺擔拞偵婲偒傞棪偑嵟傕懡偔丄巕嶦偟偺懳徾偲側傞巕嫙偼戝懡悢偑4嵥埲壓偺梒帣偱偁傞丅偦偺尨場偼80亾傑偱偑晇晈傗壟屍偺偁偄偩偺偍偲側偺栤戣偱偁傝巕嫙偲偼娭學偺側偄偙偲偑埑搢揑偵懡偄丅巕嶦偟帺嶦乮曣巕怱拞乯偺曣恊偺摿挜偲偟偰偼丄25嵥偐傜34嵥傑偱偺庒偄曣恊偑懡偄丅13嵥埲壓偺巕嫙傪嶦偡偲偄偆偺偼丄暷崙偱偼慡嶦恖憤悢偺4.3亾偵偡偓側偄偑丄擔杮偺応崌丄嶦偝傟偨巕嫙偺愨懳悢偙偦彮側偄偑丄13嵥埲壓偺巕嶦偟偼慡嶦恖憤悢偺25亾偲偄偆堎忢側崅棪傪帵偟偰偄傞丅
曣恊偵傛傞巕嶦偟帺嶦乮曣巕怱拞乯偼20悽婭偵擖偭偰偐傜懡偔側偭偨丅峏偵丄愴慜偺擔杮偺堦壠怱拞偼昻嬯偑埑搢揑側尨場偱偁偭偨偑丄愴屻偺斏塰偟偨擔杮偱偼丄壠掚晄榓丄壠掚晄埨掕丄曣恊偺忣弿忈奞偵傛傞巕嶦偟偑懡偔側偭偰偒偨丅擾懞恖岥偺戝搒夛傊偺媫懍側堏摦偵傛傝丄抧曽偐傜堏廧偟偨抝彈偼椉恊丄恊愂丄桭恖払偐傜愗傝棧偝傟偰搒夛偲偄偆恀嬻抧懷偵偍偐傟傞丅偙偺傛偆側恀嬻忬懺偼怴堏廧幰偺嵢亖曣恊偵傕偦偭偔傝摉偰偼傑傞丅傾僷乕僩傗岞抍廧戭丄峹奜偺怴嫽廧戭嬫側偳偵廧傓妀壠懓偼堦庬偺慳奜廤抍偱偁傝丄庡晈傪屒棫偝偣傞梫慺偑嫮偄丅堢帣偺栤戣丄壠帠慡斒偺愗傝傑傢偟側偳慡偰堦恖偱偟側偗傟偽側傜側偄庡晈偵偲偭偰棅傞傋偒傕偺偼丄偐庛偄帺暘偺傒偱偁傞丅偙偺揰丄壠掚偺奜偱摥偔庡晈偵偼帺嶦傗巕嶦偟偑旕忢偵彮側偄偲偄偆帠幚偼拲栚偵抣偟傛偆丅巕嫙傪堢偰傞偙偲偵偟偐帺屓幚尰偺梸朷傪帩偨偸曣恊偼丄巕嫙偺揗垽偵娮傝丄帺屓偺恖奿偲巕嫙偺恖奿傪愗傝棧偟偰峫偊傜傟側偔側偭偰偔傞丅偩偐傜偙偦丄巕嶦偟傪偡傞曣恊偺杦偳偑巕嶦偟傪嶦恖偲峫偊偰偄側偄丄偲偄偆強偵揗垽揑曣惈幮夛偺婋尟惈偲栍揰偑傒傜傟傞丅偦偟偰偦偺拞偵丄擔杮宆乽垽偲巰乿偺戝偒側柕弬偲庛偝偑偵偠傒弌偰偄傞偲峫偊傜傟傞丅悢審偺乽巕嶦偟帺嶦乿乮曣巕柍棟怱拞乯傪惗傫偩杒暷偺堏廧幰幮夛偺戝偒側壽戣偺堦偮偱傕偁傠偆丅
丂
乽垽偟偡偓傞彈乿偐傜乽垽偡傞彈乿傊
曚愊 桼棙巕
東栿壠
僋儕儞僩儞戝摑椞偺彈惈僗僉儍儞僟儖傪尒側偑傜丄僸儔儕乕晇恖偺怱嫬偵巚偄傪抷偣偰偄傞丅偙偺慜偁傞廡姧帍傪尒偰偄傞偲丄乽傕偲傕偲傾儊儕僇偺執戝偝偼幫偡偙偲偵偁傞丅僸儔儕乕偑幫偣傞側傜丄変乆偑偳偆偟偰幫偡偙偲偑弌棃側偄偺偐丅乿偲偄偆堄尒偑弌偰偄偨丅僸儔儕乕晇恖偑崱夞偺晇偺廥暦偵偳偆懳張偡傞偐偼丄傑偝偵傾儊儕僇崙柉偺憤堄傪嵍塃偡傞偺偩丅
巹偺僸儔儕乕晇恖娤偼乽垽偟偡偓傞彈乿偱偁傞丅斵彈偑偳傫側偵晇傪巟偊偰棃偨偐偼巹偑偙偙偱尵偆傑偱傕側偄丅僸儔儕乕偑偄側偐偭偨傜僋儕儞僩儞戝摑椞偼抋惗偟側偐偭偨偲偄傢傟傞傎偳丄斵彈偡傋偰偺柺偱斵偺昅摢傾僪僶僀僓乕偱偁傝丄塣柦嫟摨懱偩偭偨丅偮偄嵟嬤傑偱斵彈偼丄搙廳側傞彈惈娭學偺媈榝偵懳偟偰抐屌偲偟偰晇偺惓媊傪怣偠丄惌揋偺悌偩偲庡挘偟偨丅巹側偳丄帠幚偼偳偆偁傟丄偦偺巔偵偒傝傝偲偟偨偁傞庬偺偡偑偡偑偟偝偝偊姶偠偨傕偺偩丅
偟偐偟巹偼丄斵彈偼傕偆乽垽偟偡偓傞彈乿傪崀傝偨偺偱偼側偄偐丄偲姶偠傞丅傕偆斵彈偼晇傪巟偊偒傟側偔側偭偨丅偦偆尒偊傞偺偼巹偺嶖妎偩傠偆偐丅僋儕儞僩儞偑僗僉儍儞僟儖偺塓拞偱傕傑偩徫偄婄傪尒偣傞偺偲偼懳徠揑偵丄僸儔儕乕偺昞忣偼旀傟偰峝偔丄斶偟偦偆側桪偟偝偝偊偐偄傑尒偊傞丅崱傑偱尒偣偰偄偨晇傪巟偊傞丄帺怣偺偁傞丄偟偭偐傝幰偺乽戝摑椞偺嵢乿偺婄偱偼側偄丅
乽垽偟偡偓傞彈偨偪乿乮撉攧怴暦幮乯傪彂偄偰乽乣偡偓傞彈乿偲偄偆尵梩偺棳峴偺尦傪偮偔偭偨儘價儞丒僲乕僂僢僪偼丄傑偊偑偒偱偙偆弎傋偰偄傞丅乽巹偑亀垽偟偡偓亁偺杮幙傪棟夝偡傞傛偆偵側偭偨偺偼丄抝惈偺僋儔僀傾儞僩乮拲丗偙偺応崌偼傾儖僐儂儕僢僋乯偺嵢傗楒恖傪捠偟偰偩偭偨丅斵彈偨偪偺宱楌偼師偺傛偆側偙偲傪梇曎偵暔岅偭偰偄偨丅斵彈偨偪偑僷乕僩僫乕偺媬嵪揑栶妱傪壥偨偡夁掱偱宱尡偡傞丄桪墇姶偲嬯捝偺椉曽傪丄斵彈偨偪帺恎偑偄偐偵媮傔偰偄傞偐丄傑偨丄壗偐偺拞撆姵幰偱偁傞僷乕僩僫乕偵丄斵彈偨偪偑偄偐偵亀拞撆亁偟偰偄傞偐傪丅乿
偮傑傝丄傾儖僐乕儖傗僊儍儞僽儖丄彈惈丄巇帠側偳偵歯暼乮埶懚乯偡傞抝惈偺懁偱丄斵傜傪媬偍偆偲偟偰昁巰偵側偭偰偄傞彈惈丄斵彈偨偪偼傕偲傕偲撪柺偵晄埨傗嬻嫊姶傪書偊偰偦傟傪僐儞僩儘乕儖偟偨偄偺偩偑丄埶懚徢幰傪僐儞僩儘乕儖偡傞偙偲偵歯暼偟偰丄傕偆堦恖偺乽垽偟偡偓傞乿偲偄偆埶懚徢幰偵側傞偺偩丅偙偺帪擇恖偺娫偵弌棃忋偑傞偺偑嫟埶懚偲偄偆敍傝崌偆恖娫娭學偱偁傞丅
巹偼僸儔儕乕晇恖偑杮摉偵嬻嫊姶傪書偊偰偄傞偺偐偳偆偐偼抦傜側偄偑丄偳偆傕斵彈傪尒偰偄傞偲丄彈惈歯暼傪帩偭偨晇偺晄巒枛傪寽柦偵庢傝慤偭偰偄傞偗側偘側恖偲偄偆姶偠偑偡傞丅偟偐偟傾儖僐乕儖埶懚徢偺晇傪帩偭偨嵢偑偦偺晇偺悽榖傗偒傪偡傞偙偲偱傑偡傑偡埆壔偝偣傞傛偆偵丄斵彈偺峴摦傕丄彮偟傕晇偺栤戣偺夝寛偵側偭偰偼棃側偐偭偨傛偆偵傒偊傞丅
巻柺偑尷傜傟偰偄傞偺偱偙傟埲忋偺偙偲偼彂偗側偄偑丄巹偼僸儔儕乕晇恖偺偙偲傪彂偄偨偺偱偼側偄丅巹偼丄戝摑椞晇嵢偑杮棃庘偟偝傗晄埨傪枮偨偟偰偔傟傞傋偒垽偺偁傞恖娫娭學傪乽垽偡傞恖乿偲偺娫偵摼傜傟側偔偰丄偦偺嬻嫊姶傗晄埨傗庘偟偝傪丄巇帠丄傾儖僐乕儖丄忣帠丄巕嫙丄僊儍儞僽儖丄攦偄暔丄側偳偱枮偨偦偆偲偟偰偄傞尰戙恖偺徾挜偺傛偆偵尒偊偨偙偲傪彂偒偨偐偭偨偺偩丅偦偟偰丄撪柺偺嬻嫊偼帺暘傪垽偡傞偙偲偑弌棃側偗傟偽寛偟偰枮偨偝傟側偄偙偲丄帺暘傪垽偡傞偙偲偑弌棃側偗傟偽憡庤傪垽偡傞偙偲傕弌棃偼偟側偄偙偲傪尵偄偨偐偭偨偺偩丅
嵟屻偵丄嵟嬤弌惾偟偨僙儈僫乕偱抦偭偨帺暘傪垽偟巒傔傞偨傔偵桳岠側帺屓埫帵偺尵梩傪徯夘偡傞丅帺暘傪愑傔偨偔側偭偨帪丄嵾埆姶傪姶偠偨帪丄偄傗偵側偭偨帪丄帺暘偵岦偐偭偰尵偭偰偁偘偰傎偟偄丅枅擔壗搙偐孞傝曉偡偲椙偄丅傕偪傠傫抝惈偵傕桳岠偱偡丅
乽巹偼丄偳傫側偵巹傪棟夝偱偒側偔偲傕丄巹傪偦偺傑傑庴偗擖傟丄垽偟偰偄傑偡丅乿
丂
壜垽偄埆彈
彑扟 桼旤巕
俫俬俠夛堳
堦斒揑側尒曽偱偁傞偲巚偆偑丄俆侽戙偵傕側傞偲丄巹払偼垽忣偺宍偺曄壔偵彮偟偢偮婥偯偒巒傔傞丅俆侽戙偲尵偆偲岅暰偑偁傞偐傕抦傟側偄丅嶐崱丄巹帺恎偑姶偠巒傔丄傑偨桭恖偺垽忣栤戣偱怓乆偲峫偊偝偣傜傟傞婡夛偑憹偊偰棃偨偨傔偐傕抦傟側偄丅
崅峑傪懖嬈偡傞帪丄巹偼壗恖偐偺恊偟偄愭惗偵丄巹偺偨傔偵壗偐堦昅彂偄偰梸偟偄偲偍婅偄偟偰傑傢偭偨丅偳偺愭惗傕奆夣偔僆乕働乕偟偰壓偝偭偰丄師乆偵巹傪屇傫偱巚偄巚偄偺撪梕偺傕偺傪庤搉偟偰壓偝偭偨丅摉帪偺愭惗曽偼妱崌擭楊偑庒偔丄巹払17丄8嵥偺彈妛惗偵偲偭偰偼丄摬傟偺揑偱偁偭偨傝丄斸敾偺揑偱偁偭偨傝丄偲偵偐偔擌傗偐側彈妛惗払偺榖戣偺拞怱偱偁偭偨丅妛峑偺庼嬈傗僋儔僽妶摦埲奜偱傕丄偍怘帠傗壒妝夛丄僉儍儞僾丄僴僀僉儞僌摍傊僌儖乕僾傪嶌偭偰偼愭惗曽偲傛偔弌偐偗偨丅偦傫側帠傕偁偭偰偐巹払偼丄愭惗偲惗搆偲尵偆傛傝傕愭攜丄屻攜偲尵偆偐丄傓偟傠擭忋偺偍桭払偲偄偆娫暱偺傛偆偵偝偊姶偠偰偄偨丅
暿傟傪惿偟傓挿偄庤巻傪彂偄偰壓偝偭偨傝丄傑偨偁傞愭惗偼恖惗偺嫵孭傪戲嶳暲傋偰壓偝偭偨丅嵟屻偺曽偵庢偭偰偍偄偨巹偑堦斣婥偵側傞愭惗偐傜偺尨峞梡巻傪嫻傆偔傜傑偣偰偦偭偲奐偄偰傒傞偲丄乽抝傪崲傜偣側偄彈偼枺椡偑側偄傛丅乿愭偢丄偦偆彂偒弌偟偰丄僣儔僣儔偲尨峞梡巻4丄5枃偵傢偨傝枺椡揑側彈惈偵側傞偨傔偺旈實乮丠乯偑彂偐傟偰偁偭偨偺偱偁傞丅偱偼嵶偐偄晹暘傪巚偄弌偣側偔偰巆擮偩偑丄偦偺愭惗偑嫵偊巕払偵憽傞尵梩偲偟偰忢乆峫偊偰偄偰壓偝偭偨帠側偺偐傕抦傟側偄偲巚偄丄旕忢偵姶寖偟偨丅恊偺棫応偐傜尒偨傜丄彈妛峑偺嫵巘偑惗搆偵偙傫側尵梩傪憽傞摍偲傫偱傕側偄偲搟傞偐傕抦傟側偄丅偟偐偟丄巹偵偲偭偰偼偲偰傕栶偵棫偪丄怓乆偲栚妎傔偝偣偰懻偒丄崱偱傕姶幱偟偰偄傞偺偱偁傞丅乽彈惈偼偁傞帪丄掱傛偔埆彈偱偁傟乿偲嫵偊偰偄偨丅偳偆偄偆栿偐巹偼偦偺晹暘傪嫻偵偟偭偐傝偲崗傒崬傫偱偟傑偭偨丅
晝傪愴憟偱朣偔偟偰偟傑偭偰偄偨巹偼丄晝曣偺垽忣偺傗傝偲傝傪娤嶡偡傞婡夛偑側偐偭偨偨傔偐丄桭恖払偲斾傋傞偲丄巹偺抝彈娫偺垽忣偵娭偟偰偺栚妎傔偼偢偭偲抶偄曽偱偁偭偨丅庒偄崰偺巹偼丄愭惗偺偦偺尵梩傪嫻偵偟傑偄巚偄擸傫偱偄偨丅戝掞偺帠偼夝傜側偗傟偽捈偖偵幙栤偟偰偄偨巹偱偁傞偺偵丄偙偺帠偵娭偟偰偼壗屘偐抪偢偐偟偝偑愭偵棫偭偰丄岥偵偡傞偙偲偑弌棃偢偵偄偨丅偦偺偆偪丄庡恖偲抦傝崌偄寢崶偟偨丅栜榑丄偦傟偐傜傕愭惗偺尵梩偼偟偭偐傝偲嫻偵偟傑偭偰偁偭偨丅
偨偩埆彈偲偄偭偰傕丄杮摉偵奞傪傕偨傜偡偄傗乕側埆彈偲僄儞僕僃儖偺傛偆側乽壜垽偄埆彈乿偑偁傞丅彮偟偩偗変樤傪尵偭偰傒偰偼屻偱晇偺斀墳傪傒偰偨偭傉傝垽忣傪昞偡丅垽忣偺巺傪僺儞偲堷偒崌偭偰丄岦偆懁偺憡庤偺懚嵼傪妋偐傔崌偆丅巹偼偦傫側壜垽偄埆彈偵偪傚偭偲偩偗側偭偰傒傛偆偐側偲巚偭偨丅僴僀僴僀彈朳偼丄晇偺僄僑傪枮偨偡偩偗偱挿偄栚偱尒傞偲杮摉偺儀僞乕僴乕僼偵偼側傟側偄丅墢偁偭偰晇晈偵側偭偨偺偩偐傜丄擇恖偱堦弿偵峫偊丄偦偟偰傾僋僔儑儞傪庢偭偰恖惗偺曌嫮傪偟丄惉挿偟偰備偒偨偄偲巚偆丅晇晈偺娫偱墘偠傞壜垽偄埆彈丄偦傟偼揔摉偵晇偵巋寖傪梌偊丄婌傃傕傕偨傜偡寬峃側儔僽僎乕儉偱偁傞丅栜榑丄愭惗偺尵梩偺傛偆偵乽偁傞帪丄掱傛偔乿傪庣傜側偗傟偽側傜側偄丅
偮偄嵟嬤丄巹偺桭恖偵崲偭偨帠偑婲偒偨偺偱偁傞丅桭恖偺晇偵庒偄夁寖側壜垽偄埆彈偑弌尰偟丄偁偭偲偄偆娫偵晇偼斵彈偵枺偣傜傟偰偟傑偭偨偺偱偁傞丅暦偗偽30擭娫傕攟偭偨垽偺憙傪僩儖僱乕僪偺擛偔儉僠儍僋僠儍偵偐偒傑傢偟丄晇傪偝偭偲楢傟嫀偭偰偟傑偭偨偺偱偁傞丅巆偝傟偨嵢偲柡偼帠偺惉傝峴偒偵垹慠偲偟丄偦偟偰偔傗偟偝偵媰偒傢傔偒丄崿棎偟丄搑曽偵偔傟偰偄傞丅晇偺尵偄暘偼偲偄偊偽丄摉擭56嵥偵側傝丄乽傕偭偲傕偭偲庒偝傪曐偭偰偄偨偄丅斵彈偲嫃傞偲帺暘偵庒偝傪姶偠偝偣偰偔傟傞丅乿偲偐丅
彈惈偼俆侽戙偵傕側傟偽扤偱傕峏擭婜傪寎偊惛恄揑偵傕擏懱揑偵傕怓乆側忈奞偵弌夛偆丅偦傫側帪偙偦丄傗偝偟偄晇偺棟夝偲垽忣偵巟偊傜傟擇恖偱偦偺攇傪墇偊偰備偔傋偒偱偁傞偟丄抝惈偺応崌偱傕峏擭婜偲偼尵傢側偄傑偱傕丄傗偼傝彈惈偲摨偠傛偆偵50戙偲傕側傟偽怓乆側曄壔偑傗偭偰棃傞丅偦偟偰丄庒偝傪曐偮偺偵桇婲偵側傞條巕傕傛偔夝傞丅偟偐偟丄扤偱傕擭偼庢傞傕偺丅擭傪庢偭偨傜丄偦傟側傝偺婌傃傗妝偟傒傪尒偄弌偡傕偺偱偼側偄偩傠偆偐丅愳偺棳傟偺傛偆偵壗偵傕媡傜傢偢丄壗偐偵柍棟偵偟偑傒偮偐偢丄僗儉乕僘偵暯埨側怱偱惗偒偨偄傕偺偱偁傞丅
巹帺恎偺崱偺惗妶偺拞偱偼丄愭惗偺偁偺尵梩偼傕偆恎偵偮偄偨偺偐摿偵堄幆偟側偔側偭偰偄偨偑丄崱夞丄桭恖偺偙偺堦審偱峫偊偝偣傜傟丄媣乆偵愭惗偺尵梩傪巚偄弌偟偨偺偱偁傞丅恖偼寢崶屻丄偨偩晘偐傟偨儗乕儖偺忋傪扺乆偲憱偭偰偄偨偩偗偱丄偍屳偄偵岲偒側帠傪偟偰曢傜偟偰棃偨丅擇恖偺嫟捠偺梀傃傗妝偟傒偼摿偵側偄丅怘帠傕傑傞偱堎側傞僞僀僾偺傕偺傪岲傓偲偐丅偦傫側偵嫟捠偺傕偺偑側偄恖摨巑偑壗屘寢崶偟偨偺偐偲暦偗偽丄巇帠傪捠偟偰抦傝崌偭偨擇恖偱丄偦傟偑擇恖偺妝偟傒偱偁偭偨偑丄斵彈偼壠掚偵擖傝巕堢偰傪偟丄埨掕偟偨抔偐偄壠掚傪抸偄偰偄偨偮傕傝側偺偱偁傞丅偦偙偵尰傟偨夁寖側乽壜垽偄埆彈乿偺榖傪暦偒丄尦乆愒偄巺偱寢偽傟偰偄偨傆偨傝側偺偐側偲壗偲側偔僇儖儅揑偮側偑傝傪姶偠偰偄偨丅偲偵偐偔丄桭恖偑壗偲偐偙偺戝攇傪忋庤偵忔傝墇偊偰丄斵彈偺嵃偺惉挿偵栶棫偰偰梸偟偄偲婅偭偰偄傞丅
偁傟偐傜3儢寧傎偳偟偰丄桭恖偵夛偆偲丄嬃偄偨帠偵帠懺偼堦曄偟偰丄壗偲偦偺庒偄埆彈偼婥偵擖偭偨廇怑愭偑傒偮偐傝丄懠偺抧偵堏偭偰偟傑偄丄斵彈偲嫃偨偄偑偨傔偵30擭偲偄偆楌巎偺偁傞壠掚傪幪偰偰峴偭偨斵偑丄崱搙偼堦恖傐偭偪偵側偭偰偄偨偺偱偁傞丅傕偆壠傊偼栠傟側偄丅柡偐傜偼乽傕偆丄巹偵夛偄偵棃側偄偱丅乿偲尵傢傟丄湵慠偲偟偰偄傞丅斵偵偲偭偰傕崱傑偱偺帺暘偺惗偒曽傪偠偭偔傝偲斀徣偟丄怴偨側帺暘傪堄幆偟偰丄恖惗傪憂傝弌偝側偗傟偽側傜側偄帪偑棃偨偺偐傕抦傟側偄丅偙傫側忬懺偵側傞慜偵丄傕偭偲傕偭偲慜偵愭惗偺尵梩傪偙偺桭恖偵暘偗偰偁偘偨偐偭偨丅乽彈惈偼偁傞帪丄掱傛偔埆彈偱偁傟乿偲丅乽壜垽偄埆彈乿偼僄儞僕僃儖側偺偩偐傜乧丅
丂
僆傾僔僗偺拠娫偨偪
嵅乆栘惉婌
僩儘儞僩堏廧幰嫤夛棟帠
僇僫僟偵廧傫偱偄傞偲丄帪乆偼擔杮傊峴偒偨偔側傝傑偡丅擔杮傊婣偭偰傕偟傚偆偑側偄偲偍偭偟傖傞曽傕偁傝傑偡偑丄巹偼傗偼傝擔杮偱偍偄偟偄傕偺傪怘傋傞偲偺偲丄桭払偵夛偆偺偑妝偟傒偱偡偹丅僇僫僟偵棃傞慜偵丄廫壗擭偐丄偁傞偄偼壗廫擭偐擔杮偱惗偒偰偒偨恖惗偺偁傝曽偵墳偠偰丄恖偦傟偧傟偵偄傠偄傠側桭払偑擔杮偵偄傞偲巚偄傑偡偑丄巹偺応崌偼丄擔杮偵偄傞柡晇晈偲偐廬孼掜偨偪偼暿偲偟偰丄桭払偲偟偰偼拞妛丄崅峑偺崰偺拠娫偑堦斣偱偡丅廔愴捈屻偺媽惂拞妛偑偦偺傑傑怴惂崅峑偵側偭偨偺偱丄摨偠峑幧偱摨偠拠娫偲丄拞妛帪戙偲崅峑帪戙傪夁偛偟偨偺偱偡丅怴妰導偺攼嶈崅峑偱偡丅
偦偺崰堦弿偵妛峑怴暦傪嶌偭偨傝丄墘寑傪傗偭偨傝偟偨拠娫廫恖傎偳偑戝妛傪懖嬈偟偰娫傕側偔丄乽僆傾僔僗乿偲偄偆摨恖嶨帍傪嶌傝傑偟偨丅枅擭堦夞偩偗偺嶨暥廤偱偡偑丄堦搙傕搑愗傟偢偵崱擭偱戞38崋偵側傝傑偡丅昞巻偼奊傪昤偔偺偑岲偒側抝偑偄偰丄斵偑枅夞僗働僢僠傪採嫙偟傑偡丅報嶞偑偱偒傞偲乮嵟弶偺崰偼僈儕斉偱偟偨乯丄偦偺擭偺姴帠偑彽廤傪偐偗偰丄搶嫗偐丄搶嫗偲怴妰偲偺拞娫偺偨偲偊偽搾戲壏愹偲偐怣廈側偳偵廤傑傝傑偡丅
巹偼嶰旽嬧峴偵嬑傔偰偄傞娫傕奀奜嬑柋偑敿暘丄擔杮偱傕娭惣嬑柋偑擇夞傕偁傝傑偟偨偟丄揮怑屻偼杒暷偱偡偐傜丄僆傾僔僗偺夛偵弌惾偱偒偨偺偼敿暘傕偁傝傑偣傫偱偟偨偑丄暥廤傪捠偠偰拠娫偲偺怱偺岎棳偼偢偭偲懕偄偰偄傑偟偨偟丄擔杮傊峴偗偽昁偢扤偐偑崋椷傪偐偗偰廤傑偭偰偔傟傑偟偨丅
偙偺拠娫偼暥帤捠傝屲廫擭偺媽桭偱偡偑丄偦偙偼擔杮偺偙偲丄廤傑偭偰傕抝偩偗偱偟偨丅偲偙傠偑丄偙傟偑嶐擭偵側偭偰曄傢偭偨偺偱偡丅嶐廐巹払晇晈偼堦儢寧敿傎偳擔杮偵懾嵼偟傑偟偨偑丄偦偺帪偵巹払偺偨傔偵奐偄偰偔傟偨僆傾僔僗偺夛偵偮偄偰丄巹偑晇晈摨敽偱廤傑傠偆偲庡挘偟偨偺偱偡丅応強偼怣廈偺暿強壏愹偺屆偄椃娰偱偟偨偑丄晇恖偯傟偑擇慻尰傟傑偟偨丅斞捤偲摗揷偲偄偆偺偱偡偑丄偙偺擇恖偼悢擭慜偵擼懖拞偱偨偍傟丄儕僴價儕偱壗偲偐丄忨傪偮偒側偑傜弌曕偗傞傛偆偵側偭偨偺偱偡丅堦恖偱偼柍棟偁傞偄偼怱攝側偺偱丄晇恖偑晅偄偰偒偨偲偄偆傢偗偱偡丅
偙偆偟偰夛偵弌惾偱偒傞傛偆偵側傞傑偱偵丄擇恖偺晇恖偼憡摉嬯楯偟偨偵堘偄側偄偺偱偡偑丄擇恖偲傕偗傠偭偲柧傞偔丄抝払偲堦弿偺壏愹椃娰偺墐夛傪妝偟傫偱偄傑偟偨丅偦偺屻搶嫗偵婣偭偰偐傜丄暿偺擇恖偑晇恖偯傟偱梉怘傪嫟偵偟偰偔傟傑偟偨丅乽晇晈偱晅偒崌偍偆傛乿偲偄偆巹偺庡挘偑偡偙偟偢偮幚尰偟偨傢偗偱偡丅
拞妛崅峑埲奜偺桭恖偵偮偄偰傕丄傗偼傝嵟嬤偡偙偟偢偮曄傢偭偰偒偨傛偆偱丄楯摥慻崌偺栶堳傪偟偰偄偨崰偺拠娫偑丄晇晈偱僫僀傾僈儔椃峴偺帪偵傢偑壠偵婑偭偰偔傟偨偙偲偑偁傝傑偡丅偙偺晇晈偲偼搶嫗偱傕巐恖偱怘帠傪偡傞傛偆偵側傝傑偟偨丅僩儘儞僩偱抦傝崌偄偵側偭偨挀嵼堳偱斵傜偑婣崙屻傕擔杮偱晅偒崌偭偨傝丄僩儘儞僩傊朘偹偰棃偰偔傟偨傝偡傞桭恖傕偄傑偡偑丄偙偺恖払偲偺偍晅偒崌偄偼戝懱晇晈扨埵偱偡偹丅
偝偰丄榖偼栠偭偰丄怣廈偺壏愹偵弶傔偰晇恖楢傟偱尰傟偨斞捤偱偡偑丄偙偺壞偵晇晈偱僩儘儞僩傊朘偹偰棃偰偔傟偨偺偱偡丅傢偑傾僷乕僩偺堦奒偺僎僗僩儖乕儉偵攽傑偭偰丄僫僀傾僈儔傊峴偭偨傝丄俠俶僞儚乕偵忋偭偨傝丄堸拑傪怘傋偨傝丄晇晈擇慻巐恖偱妝偟偄擔乆傪夁偛偟傑偟偨丅斞捤偼岄偑庯枴偱丄傾儅僠儏傾偱偼嵟崅偺屲抜偺帩偪庡偱偡偑丄斵偑搢傟偰偐傜丄晇恖偑斵偵偁傢偣偰岄傪廗偄丄崱傗弶抜偺榬慜偱偡丅乮弶抜偲偄偆偺偼丄寢峔崅偄悈弨偱丄偦偆娙扨偵庢傟傞傕偺偱偼側偄偺偱偡丅乯枅擔晇晈偱屲夞偼庤崌傢偣傪偡傞偦偆偱偡丅椃峴拞傕帴愇晅偒偺実懷梡偺岄斦傪帩偭偰曕偄偰偄傑偟偨丅岄傪杮婥偱廗偭偨偩偗偱傕丄斵彈偺巚偄傗傝偑暘偐傝傑偡偑丄慺惏傜偟偄偺偼丄垽傪墴偟晅偗偢丄栚棫偨側偄巔偱斵傪彆偗偰偄傞偙偲偱偟偨丅
擔杮幃偺挬偛斞傪傢偑壠偱怘傋偰傕傜偭偨偺偱偡偑丄斵偼嵍庤偑晄帺桼偱偡偐傜丄塃庤偩偗偱怘帠傪偟傑偡丅偍拑榪偲敘偺椉曽偼帩偰傑偣傫偟丄枴慩廯側偳傕曅庤偱偼堸傒偵偔偄偺偱偡丅椬偵嵗偭偨巹偑偮偄丄偄傠偄傠庤揱偭偨傝偡傞傢偗偱偡偑丄斵彈偼偵偙偵偙偟偰丄尒偰偄偰傕庤彆偗偼偟側偄偺偱偡丅偦偺曽偑杮恖偺偨傔側偺偩偦偆偱偡丅偝傜偭偲偟偨傕偺偱偡丅
偙偺擇恖偑偝傝偘側偔彆偗崌偄側偑傜丄惗偒偰偄傞巔傪尒偰偄傞偲丄偮偄姶摦偟偰椳偑弌偰崲傝傑偟偨丅嬯楯傪忔傝墇偊偨寢壥側偺偱偟傚偆偑丄斵傜偼偛偔摉偨傝慜偺傛偆偵偟偰丄惗偒偰偄傞偺偱偡丅偍屳偄偺垽偼悈偺傛偆偵丄妸傜偐偵捠偄崌偭偰偄傞傛偆偱偡丅斵偺岥偐傜偼乽偁傝偑偲偆乿偺尵梩偑帺慠偵棳傟弌偰偄傑偟偨丅偳偆偄偆傢偗偐丄擔杮恖抝惈偼偙傟偑壓庤偱偡偐傜偹丅巹側偳傕丄嵢偵乽偁傝偑偲偆乿傪偄偆傋偒婡夛偑丄枅擔悢偊愗傟側偄傎偳偁傞偺偱偡偑丄側偐側偐岥偐傜弌偰偙側偄偱崲偭偰偄傑偡丅偙傟偱傕彮偟偼傑偟偵側偭偨曽偱丄庒偄崰偼傕偭偲傂偳偐偭偨偱偡偹丅
斞捤晇晈偼俶俿俿傪儕僞僀傾偟偰丄嵟廔嬑柋抧偱偁偭偨挿栰巗偵廧傫偱偄傑偡偑丄棃廐偼巹払偑朘偹偰峴偭偰丄怣廈奺抧傪埬撪偟偰傕傜偄乮晇恖偑幵傪塣揮偡傞偺偱偡乯丄嵞棃擭偺壞偵偼丄傕偆堦慻僆傾僔僗偺晇晈傪桿偭偰丄僇儖僈儕乕偱棊偪崌偄丄巹偑僶儞傪塣揮偟偰儘僢僉乕傪埬撪偡傞栺懇偱偡丅崱偐傜妝偟傒偱偡丅
丂
晄壜巚媍側傕偺丄偦傟偼乽垽乿
僒儞僟乕僗媨徏
宧巕
俫俬俠夛堳
偙偺壗儢寧偺娫丄儊僨傿傾娭學偵枅擔柤慜偺弌側偐偭偨擔偼側偐偭偨恖偨偪偲偄偊偽丄尵傢偢偲 抦傟偨價儖丒僋儕儞僩儞偲儌僯僇丒儖僂傿儞僗僉乕偺2恖偩傠偆丅
嬃偔傎偳忣曬栐偺敪払偟偰偄傞嶐崱偱偼丄僗僉儍儞僟儖偺撪梕偼弖帪偵悽奅傪嬱偗弰傝丄恖乆 偼偦偺徻嵶傪攃埇偡傞偙偲偑偱偒傞丅9寧拞弡偵弌偝傟偨帠審偺曬崘彂偼445儁乕僕偲偄偆朿戝 側傕偺偱偁偭偨偑丄僀儞僞乕僱僢僩偵嵹偣傜傟偨偨傔丄摉慠側偑傜扤偱傕偑梕堈偵傾僋僙僗壜擻偱偁 傞丅
偙偺帠審偺堦斣偺妀怱偼丄堦尵偱尵偊偽戝摑椞偑彈惈娭學偵娭偟乽塕傪尵偭偨偙偲乿偵恠偒傞 偺偩偑丄旝偵擖傝嵶偵搉偭偨戝摑椞偲庒偄柡偲偺娭學偼丄傑傞偱億儖僲偱傕尒偰偄傞偐偺傛偆偵丄 乽僀僢僸僢僸僢乿乽僂僢僼僢僼僢乿偲偄偭偨巚偄偱堦斒偺恖偨偪偼撉傫偩偲偄偆丅
僋儕儞僩儞傕偙偙傑偱捛偄崬傑傟傞偲偼寁嶼偟側偐偭偨偺偐丄栚偺壓偺偨傞傒傗旀楯偺偁傑傝媫寖 偵憹偊偨傛偆偵尒偊傞敀敮偑捝乆偟偄傎偳偩偑丄帺嬈帺摼偺曬偄偲偄偍偆偐丄俆侽偯傜壓偘偨戝偺 抝偺怟怈偄側偳扤傕偱偒偼偟側偄丅
偟偐偟偙偺僗僉儍儞僟儖偱堦斣彎傪庴偗偨偺偼戝摑椞偺堦恖柡僠僃儖僔乕偱偼側偄偐偲偼丄嫲 傜偔扤偱傕偑巚偭偰偄傞偙偲偩傠偆丅傕偪傠傫僸儔儕乕晇恖偺婥帩偪傕偄偐偽偐傝偐偲嶡偡傞偵梋傝偁 傞偑丄壗傫偲偄偭偰傕"偁偺晇恖"偺偙偲丄偦偆娙扨偵偼嵙偗乮偔偠乯偗偦偆偵偼側偄丅
曬崘彂偑敪昞偝傟傞埲慜偵帵偟偰偄偨晇傪巟偊傞偑偛偲偔偺僷僽儕僢僋偱偺巔惃偲丄巹惗妶偱偺 2恖偺娭學偼丄塮夋乽DAVE乿偺傛偆偵丄寛偟偰摨偠傕偺偱偼側偄偩傠偆偙偲偼憐憸偱偒傞偑丄僋儕儞僩 儞偑戝摑椞傪帿傔偨傜暿傟傞偺偱偼側偄偐偲梊憐偡傞恖偼懡偄丅傕偪傠傫嵢側傜偦傟偱乽堦審棊 拝丅僴僀丄偍庤傪攓庁乿偱廔傢傞偐傕偟傟側偄偑丄柡偲側傟偽偦偆偼偄偐側偄丅偄偮傑偱偨偭偰傕晝 柡偺娭學偼懕偔偺偱偁傞丅
尰嵼僇儖僼僅儖僯傾偺僗僞儞僼僅乕僪戝妛偺妛惗偱偁傞斵彈偼丄儌僯僇忟偑戝摑椞偲娭學傪帩 偭偨擭楊偲傎偲傫偳嵎偑側偔丄偦傟傪巚偆偲晝恊偺嬸偐偝傪恎偵煄傒偰姶偠傞偺偱偼側偄偐偲慂偭偰 偟傑偆丅傑偟偰僋儕儞僩儞偼僙儔僺乕傪昁梫偲偡傞僙僢僋僗丒傾僨傿僋僩乮惈抆揗徢乯偲偄偆昦婥偱偼側偄偐偲傕 塡偝傟偰偄傞丅偦傟偑杮摉偐斲偐偼暿偵偟偰傕丄偙偺庤偺榖戣偼岥偝偑側偄恖偨偪偺奿岲偺僩僺僢 僋偵側傞丅慡暷偺僐儊僨傿傾儞偨偪偑丄徫偄傪桿偆偺偵巊偭偨嵽椏偺嵟崅昿搙偺婰榐傪庽棫偟偨偲 偄傢傟傞傎偳偱丄庒偄桭払偺娫偱僠僃儖僔乕偑偙偺帪婜傪偳偺傛偆偵愗傝敳偗偰偄傞偺偐偲巚偆偲丄 摨偠擭崰偺柡傪帩偮曣恊偲偟偰偼嫻偺捝傒偝偊姶偠偰偟傑偆丅
傕偪傠傫抝偲彈偺娭學偼梊憐側偳偮偐側偄丄梊婜偟側偄弌夛偄偑偁傞偐傜偙偦怱偲偒傔偔偺偱偁 偭偰丄堦搙岲偒偵側傟偽丄擭楊傕幮夛揑抧埵傕偦偺懠彅乆偺偙偲偑娭學側偔側傞椺偼懡偄丅偩偐傜 偙偦丄垽偲偼晄巚媍側傕偺偱忢幆偱偼峫偊傜傟側偄娭學傕惗傑傟傞偟丄偩偐傜偙偦丄偦偙偐傜塮夋傕 暥妛傕寍弍傕惗傑傟傞偺偱偁傞丅乽儘儕乕僞乿偟偐傝乽抯恖偺垽乿偟偐傝乽垽偟偒忣晈乿偟偐傝偱偁傞丅
傕偪傠傫壗傕僋儕儞僩儞偽偐傝偑"彈偨傜偟"偲偄偆傢偗偱偼側偔丄廃抦偺傛偆偵屘働僱僨傿乕慜戝摑 椞偲儅儕儕儞丒儌儞儘乕丄屘塅栰慜庱憡偲寍幰丄僩儖僪僅乕慜庱憡偲儕僆僫丒儃僀僪側偳丄梞偺搶惣傪栤 傢偢帪戙傪挻偊偰丄僷儚乕偺偁傞抝惈偲彈惈偨偪偲偺娭學偼枃嫇偵偄偲傑偑側偄丅 傑偨NY偺價僕僱僗儅儞丄僪僫儖僪丒僩儔儞僾傕僥僉僒僗偺愇桘墹僴乕儚乕僪丒儅乕僔儍儖傕僊儕僔儍 偺屘僷僷儞僪儗儖尦庱憡傕乽憣峟乮偦偆偙偆乯偺嵢乿傪幪偰偰丄奆庒偄墱偝傫偲嵞崶丄嵞乆崶偟偰偄 傞丅
傕偪傠傫壗傕僋儕儞僩儞偽偐傝偑"彈偨傜偟"偲偄偆傢偗偱偼側偔丄廃抦偺傛偆偵屘働僱僨傿乕慜戝摑 椞偲儅儕儕儞丒儌儞儘乕丄屘塅栰慜庱憡偲寍幰丄僩儖僪僅乕慜庱憡偲儕僆僫丒儃僀僪側偳丄梞偺搶惣傪栤 傢偢帪戙傪挻偊偰丄僷儚乕偺偁傞抝惈偲彈惈偨偪偲偺娭學偼枃嫇偵偄偲傑偑側偄丅 傑偨NY偺價僕僱僗儅儞丄僪僫儖僪丒僩儔儞僾傕僥僉僒僗偺愇桘墹僴乕儚乕僪丒儅乕僔儍儖傕僊儕僔儍 偺屘僷僷儞僪儗儖尦庱憡傕乽憣峟乮偦偆偙偆乯偺嵢乿傪幪偰偰丄奆庒偄墱偝傫偲嵞崶丄嵞乆崶偟偰偄 傞丅
幮夛妛幰偵傛傞偲偦偆偟偨尃椡偺偁傞抝惈偵傛傝偐偐傝偨偄偲偺巚偄偼丄懡偔偺彈惈偺拞偵偁傞 帺慠偵旛傢偭偰偄傞惈暼偱丄備偊偵丄嬃偔傎偳擭忋偺抝惈偲嬃偔傎偳庒偄彈惈偲偺僇僢僾儖偑惗傑 傟偨傝丄傑偨"塸梇怓傪岲傓"偺尶捠傝丄愄偐傜幮夛揑抧埵偑偁傞抝惈偵偼丄彈惈偑婑偭偰棃傞偺偑 悽偺廗偄偲偄偆偙偲偵側偭偰偄傞偦偆偩丅
偨偟偐偵擭忋偺棊偪拝偄偨婛崶抝惈偼丄悽娫抦傜偢偺庒偄柡偵偲偭偰偼埨怱偲怣棅傪偁偨偊偰 偔傟傞棅傕偟偄懚嵼偵堘偄側偄丅儌僯僇忟偵偟偰傕丄寢壥偼"朶業"偲偄偆尵梩偵摍偟偄傕偺偵側偭偰 偟傑偭偨傕偺偺丄嵟弶偼悽奅偱堦斣僷儚乕偺偁傞抝惈偲娭學傪帩偭偨偙偲偵怱掙嬃偒丄偦傫側帺暘 偵悓偄偟傟側偑傜丄傕偟偐偟偨傜寢崶傕晄壜擻偱偼側偄偲堦搑偵巚偭偨偺偩傠偆丅
僫僀乕僽偲偄偊偽梋傝偵傕僫僀乕僽偩偑丄偨偐偩偐俀侾嵨偺悽娫抦傜偢偺柡傪扤偑愑傔傜傟傞偩 傠偆丅斀柺帺暘偺棫応傪棙梡偟偰丄傂偨傓偒側梒偝傪楳乮傕偰偁偦乯傫偩戝摑椞偲偄偆拞擭抝偺嗦偝 偺岟嵾偼壗偲偄偭偰傕戝偒偄丅
楒垽偼恖惗偺嵟椙偺嫵巘偱偁傞偲偼帺懠嫟偵擣傔傞傕偺偩偑丄偙偺僗僉儍儞僟儖偱偼儌僯僇忟 偑幐偭偨傕偺偼摼偨傕偺傛傝傕偼傞偐偵懡偄婥偑偡傞丅
偟偐偟丄偨偲偊偙傫側捖晠側娫暱偱傕偍屳偄偵岲傕偟偄偲巚偄丄椉幰崌堄偺忋偱偺娭學側傜丄偦 傟偼偦傟偱抝偲彈偺堦偮偺垽偺宍側偺偩傠偆丅 惤偵晄壜巚媍側傕偺丄偦傟偼乽垽乿偱偁傞丅
丂
抝偲彈
晲揷 恀棦
HIC夛堳丄儅儈乕僘夛挿
挬擔怴暦幮偑枅擭峴偆崙柉堄幆挷嵏偼丄崱擭偼乽抝偲彈
曄傢傞垽偺宍乿偲戣偝傟丄側偐側偐嫽
枴怺偄寢壥偩偭偨偺偱丄娙寜偵徯夘偡傞偲嫟偵丄巹偺恎曈偵傒傞乽抝偲彈乿偵傑偮傢傞偍榖傕暪偣偰徯夘偟偨偄丅
亀偁側偨偼"寢崶"偲偄偆尵梩偵偳傫側報徾傪帩偭偰偄傑偡偐丠亁偲偄偆幙栤偵懳偡傞夞摎偼乽愑
擟乿傪昅摢偵乽嫟摨惗妶乿乽怴偟偄恖惗乿乽岾偣乿乽擡懴乿偲懕偄偨丅彈惈偺夞摎偱偼乽擡懴乿偑抝惈偺
偦傟偵斾傋嵺棫偭偰懡偐偭偨丅
師偵亀晇晈偼"堦怱摨懱"偑傛偄偐丠偦傟偲傕姳徛偟側偄晹暘偑偁傞傋偒偐丠亁偱偼丄夞摎偼悇應捠傝屻幰偑7妱傪愯傔丄"堦怱摨懱"偑巰岅偲側傝偮偮偁傞偙偲傪帵偟偨丅偦傟偱傕丄"巰屻"偼8妱偑
堦弿偵曟偵擖傞偙偲傪朷傫偱偄傞丅
懕偄偰亀"垽忣"偼偳傫側宍偱昞偡偺偑傛偄偐丠亁偵偍偄偰偼丄乽壠掚撪偺嫤椡乿乽偪傚偭偲偟偨婥
攝傝乿偑埑搢揑偵懡偐偭偨丅乽僗僉儞僔僢僾乿傗乽僾儗僛儞僩乿摍偺夞摎偑1妱偵傕枮偨側偄偺偼丄巹偺梊憐偵斀偡傞偲偙傠偩丅
偝偰丄偙偺傾儞働乕僩偱堦斣嫽枴怺偐偭偨偺偑師偺"棧崶"偵偮偄偰丅乽棧崶偟偰傕傛偄乿偑慡懱偺
6妱偱丄斀懳攈偺2攞丅96擭偵偼丄幚嵺偺棧崶審悢傕1899擭偺挷嵏奐巒埲棃嵟崅傪婰榐偟丄
摿偵寢崶偟偰20擭埲忋偨偮晇晈偺"弉擭棧崶"傕夁嫀嵟崅偲側傝丄棧崶慡懱偺16亾傪愯傔偰偄偨丅
偦傟偱傕丄亀"巕嫙"偑晇晈偺側偐傪偮側偓偲傔偰偄傞偐丠亁偱偼丄僀僄僗偑7妱嫮偁偭偨偺偱丄巕嫙
偑偄側偗傟偽偙偺悢偼傕偭偲忋偑偭偰偄偨偐傕偟傟側偄丅
嵟屻偵"晄椣"偵偮偄偰丅偙傟偼擔暷斾妑偱昞偝傟偰偍傝丄岲姶偺傕偰傞恖偐傜晄椣偺岎嵺傪桿
傢傟偨応崌丄擔杮偱偼3妱埲忋偑乽怱偑摦偔偲巚偆乿偲摎偊偨偺偵懳偟丄暷崙偱偼乽慡偔墳偠側偄乿偑
7妱嬤偐偭偨丅傑偨丄晄椣偑乽偳傫側応崌偱傕嫋偝傟側偄乿偲摎偊偨偺偑擔杮偱偼5妱偵枮偨側偐偭
偨偑丄暷崙偱偼慡偰偺擭楊憌偱7妱傪墇偊丄擔杮偲偺堘偄偑嵺棫偭偨丅
嶐擭4寧偐傜乽儅儈乕僘乿偲偄偆怴暷儅儅偝傫偺巕堢偰僒乕僋儖傪奐巒偟偨丅擔杮岅傪榖偡曣恊
偺拠娫傪憹傗偡偺偑栚揑偱丄崱偱偼夛堳傕30柤梋傝偲戝強懷偵側偭偨丅枅寧偺儈乕僥傿儞僌偱偼丄
巕堢偰偵尷傜偢丄"晇晈偘傫偐""壠懓寁夋""僗僩儗僗夝徚朄"側偳丄偱偒傞偩偗柺敀偄僥乕儅偵偮偄偰榖偟崌偭偰偄傞丅
偳傫側榖戣偵偟偰傕懡偐傟彮側偐傟晇偺榖偑弌偰偔傞丅偪側傒偵晇偼擔杮恖偵尷傜偢條乆側僶
僢僋僌儔儞僪傪傕偮丅嬻峘偱弌夛偭偨偲偄偆儘儅儞僥傿僢僋側僇僢僾儖偐傜丄僇僫僟偵堏廧偟偨偄偑偨
傔偵柪偭偨偁偘偔晇傪棙梡偟偨宍偱寢崶偟偨僇僢僾儖乮晇傕偆偡偆偡姶偠偰偄傞偦偆偩偑丄崱偱偼巕
嫙傕偄傞乯丄楒垽摉帪偼傾僣傾僣偩偭偨偺偵丄巕嫙偑偱偒偰埲棃偡偭偐傝晇晈拠偑埆偔側偭偨僇僢僾
儖丄偦傫側忬嫷傪偍偦傟偰巕嫙傪嶌傠偆偲偟側偄僇僢僾儖丄崱偩偵枅擔丄晇偑婣傞偲僴僌偲僉僗傪寚
偐偝側偄僇僢僾儖丄寢崶3擭栚偵偟偰婛偵棧崶傪峫偊偰偄傞僇僢僾儖乮偪側傒偵巕嫙傕偄傞乯摍乆丅
拞偱傕丄尦戝壠偝傫偺偛庡恖偵崱偱傕壠捓傪暐偄丄壗偐傜壗傑偱僼傿僼僥傿
僼傿僼僥傿俆侽/俆侽偲懳摍側娭學傪曐偭偰偄傞恖偺榖偼巹払傪姶怱偝偣偨丅
擔杮偱傕嬤崰丄棧崶棪偺憹壛偲嫟偵寢崶偟側偄"撈恎婱懓"偑憹偊傞孹岦偵偁傞傛偆偩丅傑偨丄
"摨惈垽"偵懳偡傞庴偗擖傟傕姲梕偵側傝偮偮偁傞丅妋偐偵摨惈偲偍拑偡傞曽偑妝偟偄偟丄憡庤偺
婥帩偪傕棟夝偟傗偡偄偲巚偆丅偱傕丄偣偭偐偔恄條乮丠乯偑偙偺悽偵俀偮偺堘偆"惈"傪憂憿偝傟偨偺偩偐傜丄堎惈偲忋庤偵晅偒崌偄偨偄丅偦偟偰墢偁偭偰寢偽傟丄抸偒忋偘偨"壠掚"側偺偩偐傜丄偑傫偽
偭偰堐帩偟偰備偙偆丅偐偲偄偭偰堦搙偒傝偺恖惗偩偐傜丄"擡懴"偱廔傢傜偣傞偺偼傕偭偨偄側偄丅
塱墦偺僥乕儅偱偁傞乽抝偲彈乿丅怓乆側宍偑偁傞偩傠偆丅偙偆偁傞傋偒偩偲偼尵偊側偄偑丄傂偲傝偺
恖偵寛傔偨側傜丄偦偺恖偲"妝偟偔"帪傪夁偛偟偨偄丅偦偆偡傞偨傔偵丄"憡庤傪帺暘偲摨偠埵垽偡傞"
偙偲傪乮帪偵偼朰傟傞偙偲傕偁傞偑両乯怱偑偗偰偄傞丅
丂
垽偼栄巺偺DRAWERS
揷拞 桾夘
乽擔宯偺惡乿 曇廤幰
乽抝偲彈偺垽偺偐偨偪乿側傫偰偄偆僥乕儅偱丄幐妝墍偵傕屻妝墍偵傕峴偭偨偙偲偺側偄僆僕僒儞偼偄偭偨偄壗傪彂偗偽傛偄偺偱偟傚偆丅嶰擔傕揇徖偵偼傑傝崬傫偩傛偆偵傕偑偄偰偄傑偡傛丅偟傑偄偵偼丄偰傗傫偱偊丄垽偵僇僞僠偑偁偭偰偨傑傞傕傫偐傛丄偲傆偰偔偝傟巒傔偨傕偺偱偡丅
偦偆偱偡傛丅乵垽乶側傫偰偄偆偙偺忋傕側偔宍帶忋妛揑側僐僐儘偺拞恎偵柍棟傗傝僇僞僠傪梌偊傛偆側傫偰偡傞偲丄偄偒側傝宍帶壓側僇僞僠偑棫偪尰傟偰偒偰偟傑偄傑偡丅偦傟偼僐僐儘偺堦斣姶偠傗偡偄晹暘傪曪傫偱偄傞傕偺偱丄偄偆側傜偽僐僐儘偺堷偒弌偟偵偟傑傢傟偰偄傞壓拝偺傛偆側傕偺偱偡丅偱偡偐傜丄僓丒儀僀偺儔儞僕僃儕乕偺峀崘傪尒傟偽傢偐傞傛偆偵丄偄傠傫側僇僞僠偑偁傞傢偗偱偡丅偦傟偱偄偰婎杮揑偵懠恖偵尒偣傃傜偐偡傕傫偱傕側偄傢偗偱丄憡庤偑偳傫側僇僞僠偺壓拝傪丄偄傗丄垽傪傑偲偭偰偄傞偐側傫偰暘偐傝傑偣傫偟丄偲傝傢偗偰嫽枴偺側偄偙偲偱偡丅偲偼尵偊丄揹幵偺拞偱側傫偲側偔壓拝偑摟偗偰尒偊傞彈惈偑栚偺慜偵棫偭偨傝偡傞偲丄乽偁傟偉丠乿偲搑抂偵偦傢偦傢偟偰偟傑偆偺偼偳偆偄偆僆僕僒儞偺怱棟側傫偱偟傚偆偹丅
尒偊偦偆偱偄偰寛偟偰慡杄傪偁傜傢偵偟偰偼偔傟側偄偺偑垽偺僇僞僠偱丄偩偐傜丄抝偲彈偼嫸偍偟偔傕媮傔崌偆偺偩側丄偲偐壗偲偐壓拝偺偪傜偟傪傔偔傝側偑傜丄堦恖偱彑庤偵擺摼偟偰偟傑偄傑偟偨傛丅
幚偼丄杔偼彈惈偺晹壆偵擡傃崬傫偱壓拝偺媗傑偭偨堷偒弌偟傪丄傑傞偱曮偺敔傪偦偭偲墴偟傂傜偔傛偆偵奐偗偰丄懅傪堸傫偱尒偮傔偨偙偲偑堦搙偩偗偁傝傑偡丅壓拝僪儘儃乕偟偨傢偗偱偼偁傝傑偣傫丅傑偩撈恎偺擇廫戙屻敿偩偭偨崰丄傛偔擔梛擔偵堦弿偵僥僯僗傪偟偰偄偨僇僆儖偪傖傫偲丄側偤偐偦偺擔偼杔偺傾僷乕僩偱椏棟傪嶌偭偰擇恖偱偍儅儅偛偲傪偟傛偆偲偄偆偙偲偵側偭偨帪偺偙偲偱偡丅斵彈偺傾僷乕僩偵偼僔儍儚乕偑側偄偺偱丄僔儍儚乕傪梺傃偨偄丄偱傕丄壓拝偺懼偊偑側偄偺丄巹偺傾僷乕僩傑偱峴偭偰庢偭偰棃偰偔傟側偄丠偲尵偄弌偟偨偺偱偡丅
惓捈尵偭偰堦弖偨偠傠偓傑偟偨偗偳偹丄乽偍偭丄偄偄傛乿偲偐側傫偲偐寉偄僲儕傪傛偦偍偭偰僶僀僋偵傑偨偑傝丄杔偼憗堫揷捠傝傪廫暘傎偳憱偭偰垻嵅儢扟偺斵彈偺傾僷乕僩傑偱峴偒傑偟偨丅偱傕丄偳偆偵傕彈惈偺晹壆偺僪傾偺尞傪奐偗偰擖傞偲偄偆偺偼屻傠傔偨偄傕偺偱偟偨丅壗屘偐僐僜僪儘偺傛偆偵懌壒傪偟偺偽偣偰偟傑偆傢偗偱偡丅
戝妛堾偵捠偆僇僆儖偪傖傫偺晹壆偼堄奜偲幙慺偱丄杒崙堢偪偵偼搶嫗偺壞偼偮傜偡偓傞偲丄恊偑攦偭偰偔傟偨偲偄偆僄傾僐儞偩偗偑侾DK偵偼晄掁崌偄偵暆傪偒偐偣偰偄傑偟偨丅栚巜偟偨僞儞僗偼偡偖尒偮偐偭偨偺偱偡偑丄偁傟偭丠忋偐傜壗抜栚偺堷偒弌偟偩偭偨偭偗丠
庢傝姼偊偢堦斣忋偺堷偒弌偟傪偦偭偲奐偗偨帪偺嬃偒傪側傫偲昞尰偟偨傜偄偄偺偱偟傚偆丅
偦偙偼傑傞偱彫偝側偍壴敤偱偟偨丅僋儖僋儖偲摏忬偵偨偨傑傟偨弮敀傗傜扺偄僺儞僋偺壴暱偺彫偝側壓拝偑棎傟側偔偒偪傫偲暲傫偱偄傞桳條偼丄杔偺憐憸椡傪偼傞偐偵椊夗偡傞傕偺偱丄偟偽傜偔惡傕側偔尒崨傟偰偄傑偟偨丅偦偟偰丄偙傟偑彫偝側僇僆儖偪傖傫偑枅擔偲偭偐偊傂偭偐偊僗僇乕僩偺壓偵晅偗偰偄傞傕偺側偺偐偲巚偆偲姶摦偡傜妎偊偨偺偱偡丅尵傢傟偨捠傝庤慜偺敀偄偺傪偡偔偆傛偆偵椉庤偱庢傝弌偟偰丄懠偺廧恖偑晄怰偵巚偆慜偵憗偔戅弌偟傛偆偲偟傑偟偨丅偲偙傠偑偳偆偟偨偙偲偱偟傚偆丅偳偆偵傕丄偳偆偵傕丄杔偺懌偼偦偺曮偺敔偐傜棫偪嫀傠偆偲偟側偄偺偱偡丅懌偑彑庤偵丄傕偆偪傚偭偲丄傕偆堦抜偩偗擿偄偰尒側偄偐偲丄杔傪偦偦偺偐偡偺偱偡丅偄傗丄懌偺偣偄偵偟偰偼偄偗側偄丅杔偼偳偆偵傕偦偺岲婏怱傪墴偟偲偳傔傞偙偲偑偱偒傑偣傫偱偟偨丅偦偟偰丄偦偭偲堦抜偢偮擿偄偰偄偭偨偺偱偡丅偡傞偲丄偲偭偰傕堄奜側傕偺偑弌偰偒偨偺偱偡丅栄巺偺僘儘乕僗偱偟偨丅偍僼僋儘偑愄偼偄偰偄偨偺偲摨偠抧枴側嵁怓偱偡丅搤偵愻戵偟偨屻丄僇僠儞僇僠儞偵搥傝偮偄偨傑傑暔姳偟儘乕僾偐傜傇傜偝偑偭偰偄偨傗偮偱偡丅柺敀偑偭偰柍棟傗傝愜傝嬋偘偨傝偡傞偲栄巺偑彎傓偺偱丄乽偪傚偟偨傜僟儊両乿偲偨偟側傔傜傟偨丄偁偺曣偺尷傝側偔傆偔傛偐側壓敿恎傪曪傫偱偄偨栄巺偺僘儘乕僗偑偙傫側偲偙傠偵偁偭偨側傫偰乧丅
億乕僢偲忋婥偟偨傑傑偺婄偱傾僷乕僩偵栠傞偲丄懸偪偐偹偰偄偨條巕偺僇僆儖偪傖傫傕側傫偲側偔億乕僢偲抪偢偐偟偦偆偵壓拝偺擖偭偨億儕戃傪庴偗庢傝傑偟偨丅偦偟偰擇恖偼壗帠傕側偐偭偨偐偺傛偆偵偍儅儅偛偲傪懕偗偨偺偱偡丅
偝偰丄偦偺屻偺擇恖偼偳偆側偭偨偐丄暦偒偨偔側偭偨丠巆擮側偑傜丄昞柺揑偵偼壗傕偁傝傑偣傫偱偟偨丅嶶曕偺嵟拞偵庤偑怗傟崌偭偰丄屳偄偵僪僉偭偲偟偨偙偲偑偁偭偨偐傕偟傟傑偣傫丅偱傕丄擇恖偲傕偁傞偲偙傠偱僉僠僢偲慄傪堷偄偰丄偦傟埲忋偼寛偟偰嬤婑傝傑偣傫偱偟偨丅偦偺曽偑丄擇恖偺娭學偵夎惗偊偰偄偨旝壏偺偸偔傕傝傪挿偔妝偟傔傞偼偢偩偲丄偟偨偨偐偵栚攝偣傕偣偢偵椆夝偟偰偄偨偐傜偩偲巚偄傑偡丅
幚偼僇僆儖偪傖傫偼丄杔偺恊桭偺尦楒恖偩偭偨偺偱偡丅斵偺揮嬑偑寛傑傝丄崶栺傪敆偭偨帪丄斵彈偼屗榝偄丄擸傫偩偡偊丄偲偵偐偔廋巑傪廔傢傜偣偨偄丄偦偺愭偺偙偲偼崱偼峫偊偨偔側偄偲抐傝傑偟偨丅偲偙傠偑丄偦偺婽楐偼師偵偲偰傕偮傜偄暿棧傪梡堄偟偰偄傑偟偨丅斵偼枹楙傪抐偪愗傞傛偆偵丄偦偺屻丄尒崌偄傪偟偰偝偭偝偲寢崶偟傑偟偨偑丄偟偽傜偔偺娫偼擇恖偲傕丄偼偨偱尒偰偄偰偐傢偄偦偆側偔傜偄棊偪崬傫偱偄傑偟偨丅杔偼偲尵偊偽丄擇恖偺娫偱乽偄偮傕柧傞偄寀岝摂乿偺栶栚傪偍偍偣偮偐偭偰暦偒栶偵揙偟偰偄偨傢偗偱偡丅偨偩幚嵺偺偲偙傠丄杔偵偲偭偰傕丄僇僆儖偪傖傫偲偺堿塭傪偮偔傜側偄娭學傪堐帩偡傞偺偼幚偼偪傚偭偲僔儞僪僀側偲丄恊桭偲偺桭忣傪偲傞偐丄帺暘偺僷僩僗傪慡偆偡傞偐偲偄偆壞栚燍愇揑乽僐僐儘乿偺僕儗儞儅傪擸傫偩帪婜傕偁傝傑偟偨丅偁偺慖戰偑惓偟偐偭偨偐偳偆偐側傫偰扤偵傕傢偐傜側偄偗傟偳丄偨偩丄抝偲彈偺垽偺僇僞僠側傫偰摓掙偦偺摉恖摨巑偵偟偐側偧傟側偄傕偺偩偲丄偦偆偮偔偯偔巚偆偺偱偡丅
偦偟偰擇廫擭丅拞擭偺偍偽偝傫偵側偭偨僇僆儖偪傖傫偼丄傑偩偁偺嵁怓偺栄巺偺僘儘乕僗傪棜偄偰偄傞偺偐側丅偪傚偭偲丄嫽枴偁偭偨傝偟偰乧丅
丂丂偐側偟傒偲尵偊偽
丂丂丂丂丂丂丂懠偐傜尒傟偽
丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂偨偩帇慄偑壓曽偵孹偔偙偲
丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂乮塱悾
惔巕丒帊廤乽挶偺缜缏乿乯
丂
曇 廤 屻 婰
崱擭偺僯儏乕僗儗僞乕偺僥乕儅偼丄HIC偑偙傟傑偱偵堦搙傕庢傝忋偘偨偙偲偑側偐偭偨乽抝偲彈偺垽乿偵偮偄偰偱偡丅夣偔婑峞傪彸戻偟偰偔偩偝偭偨曽偨偪偐傜丄屄惈偁傆傟傞寙嶌僄僢僙僀偑廤傑傝傑偟偨丅
嫽枴怺偄怱拞峫傗埶懚徢偵偮偄偰偺怺偄摯嶡丄岾偣側寢崶惗妶偺旈實傗桭恖晇晈偺怱壏傑傞垽忣暔岅丄巚傢偢悂偒弌偟偨桖夣側栄巺偺僘儘乕僘堩榖丄傑偨丄恎嬤偵孞傝峀偘傜傟傞晄椣寑偐傜僋儕儞僩儞戝摑椞偺僗僉儍儞僟儖傑偱丄偄傠偄傠側妏搙偐傜尒偨乽抝偲彈偺垽偺偐偨偪乿偑晜偐傃忋偑傝傑偟偨丅
挬擔怴暦偺傾儞働乕僩偺寢壥丄晄椣偵懳偡傞夞摎偑擔暷娫偱戝偒側嵎偑偁偭偨偙偲偼丄偲傝傢偗嫽枴傪帩偪傑偟偨丅擔杮偺堎忢側傑偱偺乽幐妝墍乿僽乕儉偑壗屘婲偒偨偐丄傢偐偭偨傛偆側婥偑偟傑偡丅
偝偰丄奆偝傫偼偙偺儐乕僗儗僞乕傪撉傫偱丄偳偆偍姶偠偵側偭偨偱偟傚偆偐丅
(僔僃儅乕 備傒)
嵟嬤乽Men are from Mars, Wemen are from Venus乿偲偄偆杮傪撉傫偩丅杮摉偵栚偐傜椮偳偙傠偐丄偦傟傑偱偺媈栤偑偡偭偒傝偟偰偄偔偺偑夣偄嬁偒偩偭偨丅抝偼壩惎恖丄彈偼嬥惎恖丄備偊偵摨惈摨巑偱偼僣乕僇乕側偺偵丄堎惈摨巑偱偼岆夝偼偍傠偐丄尵梩偺堄枴偝偊惓妋偵偼揱傢傜側偄丅偁乕偦偆偐丄偲巚偄摉偨傞帠偑悢抦傟偢丅杮摉偵撉傫偱傛偐偭偨丅偩偐傜摨惈垽偵偼偟傞恖偺婥帩偪偑壗偲側偔傢偐偭偨傛偆偩丅側偤偵丄恖偼偦傫側堄巙慳捠偺崲擄側憡庤傪慖傃丄傢偞傢偞嬯楯傪偟傚偄偙傓偺偐丠
傑偁丄偦傫側帠偼楒垽拞偵偼巚偄偮偒傕偟側偐偭偨丅乽垽乿偭偰巕懛斏塰偺偨傔偵恖偺巚峫傪恄
條偑乽偪傚偭偲僗僩僢僾乿偝偣偰偟傑偆偙偲側偺偐丅
偱傕丄偦傫側帪偲偟偰斚傢偟偄抝彈偺垽傕丄偦傟側偟偺恖惗偼敄傜姦偄峳栰偺條偐傕偟傟側偄丅
(僂僀儞僋儔乕 愮掃)
俫俬俠偱偼丄崱擭偐傜俢俿俹乮僨僗僋丒僩僢僾丒僷僽儕僢僔儞僌乯僾儘僌儔儉傪摫擖偟偰丄僯儏乕僗儗僞乕偺榞慻傒嶌傝偐傜婰帠傗峀崘偺儗僀傾僂僩傑偱丄堦娧偟偰僋儔僽撪偱弌棃傞傛偆偵側傝傑偟偨丅
偲偙傠偑丄僐儞僺儏乕僞偵岦偐偭偰偄傞偲丄晜偐傫偱棃傞偺偼巕嫙帪戙偺庤嶌傝怴暦丅僗儕儖偲幚姶偑偁傝傑偟偨丅戝偒側柾憿巻偵儅僕僢僋偱彂偒崬傫偩彫妛峑偺妛媺怴暦丅 拞妛帪戙偺僈儕斉報嶞偼丄偟偭偐傝椡傪擖傟側偄偲敄偔偰撉傔側偄偟丄椡傪擖傟夁偓傞偲尨巻偵寠偑奐偄偰傗傝捈偟丅揝昅偺僈儕僈儕柭傞壒偑帹偺墱偵傑偩巆偭偰偄傑偡丅
弶婜偺僴乕儌僯乕僯儏乕僗偼庤彂偒偱偟偨丅庤偵庢傞偲崱偱傕憂棫儊儞僶乕偺堄婥崬傒偑揱傢偭偰偔傞傛偆偱偡丅巹払偼曋棙偝偺柤偺壓偵傑偨傂偲偮戝愗側傕偺傪幐偍偆偲偟偰偄傞偺偱偟傚偆偐丅偲偼偄偊丄埲慜側傜梄憲偐庤搉偡偟偐側偐偭偨僆儕僕僫儖丒儘僑偺慛柧側僀儊乕僕偑堦弖偺偆偪偵E-mail偱撏偗傜傟傞偺傪尒傞偲丄傗偭傁傝攺庤傪憲傞巹偱偡丅
乮僐僘儘僽僗僉乕 垻晹旤抭巕乯
16擭慜偵僩儘儞僩偺擔宯幮夛偺拞偵崻傪壓傠偟偨僴乕儌僯乕丒僀儞僞乕僫僔儑僫儖丒僋儔僽(HIC)偼丄擭枅偵彮偟偢偮拝幚偵巬傪峀偘偰嶲傝傑偟偨丅巬偺峀偘曽偼偦偺擭偵傛偭偰堎側傝傑偡偑丄忢偵帺屓偺岦忋偲抧堟幮夛傊偺峷專偲偄偆2揰傪擮摢偵抲偄偰妶摦偺寁夋傪棫偰幚巤偟偰嶲傝傑偟偨丅椺偊偽崱擭傕怓乆側嵜偟暔偵嶲壛抳偟傑偟偨偑丄摿偵HIC偑嶱壓偵懏偡傞僩儘儞僩堏廧幰嫤夛(NJCA)庡嵜偺僶乕儀僉儏乕偲僀儞僼僅乕儊乕僔儑儞丒僽乕僗傊偺嶲壛丄偦偟偰搶嫗僉儍儔僶儞偺偍傕偪傖攧傝応偱偺儃儔儞僥傿傾偼壗擭傕懕偄偰偄傑偡丅
傑偨HIC峆椺偺壞偺僺僋僯僢僋丄偍抋惗夛丄僋儕僗儅僗丒僷乕僥傿乕偼儊儞僶乕摨巑偺恊杛傪恾傞栚揑偱峴偭偰偄傑偡丅峏偵崱擭偼夛堳偺傾乕僥傿僗僩偵傛傞儚乕僋僔儑僢僾傪奐巒偟丄傛傝朙偐側恖惗傪憲傞偍庤揱偄傕巒傔傑偟偨丅偦偺懠偵傕僩儘儞僩懾嵼偺擔杮恖堛巘偵傛傞媬媫朄媦傃墳媫庤摉島廗夛丄朘壛拞偺擔杮恖彈惈塣摦壠偵傛傞島墘夛傪幚巤抳偟傑偟偨丅
偦偟偰11寧偵偼擔宯暥壔夛娰偺怴娰岺帠巟墖傪栚揑偲偟偨尰戙朚妝丄惣愳峗暯傾儞僒儞僽儖偵傛傞僐儞僒乕僩偱崱擭搙偺妶摦傪掲傔妵傝傑偡偑丄悽奅嫟捠偺壒妝傪捠偟偰僩儘儞僩幮夛偵傕巹払僴乕儌僯乕丒僀儞僞乕僫僔儑僫儖丒僋儔僽偺妶摦傪抦偭偰偄偨偩偗傟偽丄偲婅偭偰偍傝傑偡丅
崱擭偺僯儏乕僗儗僞乕偺僥乕儅偼丄悢妛偺條偵柧妋側摎偊偑摼傜傟側偄丄偟偐偟嫽枴怺偄僩僺僢僋偱偁傞偲偙傠偺乽抝偲彈偺垽偺宍乿偲寛傑傝丄條乆側堄尒傗峫偊偑婑偣傜傟傑偟偨丅捛媮偡傟偽偡傞掱撪梕偑尷傝側偔怺偔側傞乽垽乿偺傛偆偱偡偑丄HIC傕崱屻塿乆拞枴偑擹偔丄墱峴偺怺偄尗柧側僌儖乕僾偵敪揥偝偣偰偄偒偨偄傕偺偱偡丅
乮僴僀僪 梕巕丄HIC夛挿乯
[尨峞偼傾儖僼傽儀僢僩弴]
HARMONYNEWS 丂1997 廐
僴乕儌僯乕丒僀儞僞乕僫僔儑僫儖丒僯儏乕僗儗僞乕 No.18
彈惈偺幮夛恑弌 僇僫僟摑寁嬊乛HI僋儔僽挷嵏偵尒傞尰忬
枹偩柾嶕偡傞懡偔偺彈惈偨偪
丂
HI僋儔僽僯儏乕僗儗僞乕15廃擭婰擮崋曇廤挿
僒儞僟乕僗媨徏宧巕
愴屻堏廧幰偺彈惈偨偪偱嶌傞HI僋儔僽偼崱擭憂棫15廃擭栚傪寎偊丄巹払偼偙傟傪婰 擮偟偰丄堦擭娫偵傢偨傝奺庬偺僀儀儞僩傪峴偄傑偟偨丅偙傟偵傛偭偰俆擭慜偺10廃擭 偵堷偒懕偒怴偨側儅僀儖僗僩儞傪抸偒傑偟偨偑丄奆條偺偛棟夝偲偛巟墖偵傛傝懡偔偺 妶摦偑弌棃偨偙偲傪姶幱偟偰偍傝傑偡丅
傑偨摉夛偱偼枅擭僯儏乕僗儗僞乕傪敪峴偟偰偄傑偡偑丄崱擭偼夛堳偵傛傞乽彈惈偺 幮夛恑弌乿偵偮偄偰偺傾儞働乕僩傪偲傝峴側偄傑偲傔偰傒傑偟偨丅偙傟偼崱廐僇僫僟 摑寁嬊偑敪昞偟偨挷嵏偲傑偭偨偔摨偠幙栤傪夛堳偵帋傒偨乮傾儞働乕僩夞廂棪90亾乯 偺偱偡偑丄摨偠僇僫僟幮夛偵惗偒傞彈惈偲偟偰偙偺栤戣傪偳偺傛偆偵峫偊偰偄傞偐嫽 枴傪帩偭偨偙偲偑偒偭偐偗偱偡丅 妋偐偵帪戙偼崱21悽婭偺懌壒偑傕偆偦偙偵暦偙偊傞帪傪寎偊丄変乆偼恀偭峏側怴悽 婭偵岦偐偭偰绨恑偟偰偄傑偡丅擔乆偺惗妶偺拞偵尒傞擔恑寧曕偺僥僋僲儘僕乕偺敪払 偵偼扤傕偑栚傪尒挘傝傑偡偑丄偩偐傜偲偄偭偰恖娫偺婎杮揑側惗偒曽偑戝暆偵曄傢偭 偨偲偼巚偊傑偣傫丅偦傟偼枹偩偵偙偺抧媴傪巟攝偟偰偄傞恖娫偵偼丄抝偲彈偲偄偆惈 偟偐懚嵼偟側偄偙偲偑堦斣偺棟桼偱偟傚偆丅
偟偐偟偦傟偱偼偦偺抝彈偺偁傝曽偼丄偦偺僥僋僲儘僕乕偺恑曕傎偳偵曄壔偟偨偱偟 傚偆偐丅傕偪傠傫偙偺乽偁傝曽乿偲偄偆堄枴偑壗傪巜偡偐偵傛傞偙偲偼妋偐偱偡偑丄 偙偙傑偱恑曕偟偨幮夛偺偦偺敪揥偺堦梼傪扴偆彈惈偺幮夛恑弌偵徟揰傪摉偰偰尒偨帪 丄傗偼傝戝偒側乽丠乿儅乕僋偑晅偐偞傞傪摼側偄偺偱偼偲巚偄傑偡丅 僇僫僟摑寁嬊偑敪昞偟偨挷嵏寢壥偼旕忢偵嫽枴偁傞傕偺偱丄曣恊偑摥偔偲偄偆偙偲 偺偦偺棤偵偳傫側棟桼偑塀偝傟偰偄傞偵偟傠丄巕嫙傪帩偭偨彈惈偑巇帠傪偡傞偙偲偺 梕堈側傜偞傞柺偑晜偒挙傝偵側傝傑偟偨丅堦岥偵傑偲傔傞偲乽曣恊偑摥偄偰壠掚偵僟 僽儖僀儞僇儉傪傕偨傜偡偙偲偼丄宱嵪柺偐傜尒偰崱偺僇僫僟偺幮夛偱偼摉慠偺偙偲偩 偑丄堦曽巕嫙乮摿偵梒帣乯偑怱攝偱偁傞偙偲傕婾傜偞傞怱棟偱偁傞乿偲偄偆偙偲偵側 傞傛偆偱偡丅傾儞働乕僩偺摎偊偼丄HIC偲僇僫僟彈惈偱戝暆偵堎側傞応崌傗丄媡偵旕 忢偵椶帡偟偰偄傞側偳偦傟偧傟柺敀偄寢壥偑弌偰偄傑偡丅傑偨丄偙偆偟偨挷嵏偼偦傟 偑偳傫側栚揑偺偨傔偵峴側傢傟傞傕偺偱偁傟丄扨偵乽僀僄僗乿乽僲乕乿偱偼摎偊傜傟 側偄懁柺傪帩偭偰偄傞偨傔巹偨偪偼夛堳偺堄尒傪揧偊傞偙偲傕帋傒丄壛偊偰僇僫僟摑 寁嬊偺挷嵏寢壥傪尒偨僞僀儉帍偺僐儔儉僯僗僩偺塻偄堄尒傕東栿偟偰嵹偣傑偟偨丅
HI僋儔僽偑偙傟偐傜20擭丄30擭偲懕偔偙偲傪婅偄側偑傜丄偦偺帪偵丄傕偟崱夞偲摨 偠挷嵏傪偟偨傜丄僇僫僟幮夛偼丄傑偨僋儔僽夛堳偺堄尒偼偳偺傛偆偵側偭偰偄傞偩傠 偆偐偲巚偄傪抷偣偰偄傑偡丅 奆條偺偛堄尒傪偍暦偐偣捀偗偨傜婐偟偄尷傝偱偡丅
幙栤侾 摥偄偰廂擖傪摼傞偙偲偼丄偁側偨偑岾偣偱偁傞偨傔偵丒丒丒
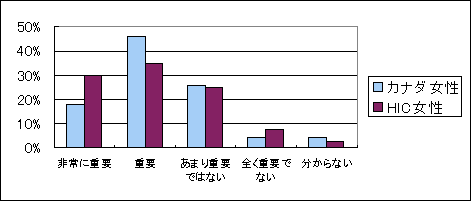
嘆 旕忢偵廳梫偱偁傞 (僇僫僟彈惈 18%, HIC 30%乯
40戙 丒偍嬥偑偁傟偽廳梫偱偼側偄丅 傑偢丄怘傋偰偄偗側偗傟偽偟偨偄偙偲傕偱偒側偄丅
50戙 丒堦斒幮夛偱抝彈丄恖庬摍傪栤傢偢丄怑応偱暯摍偵摥偗傞偲偄偆偙偲偼旕忢偵戝愗側 帠偲巚偆丅
丒乽摥偄偰廂擖傪摼傞乿偲偄偆帠偵偼戝偒側愑擟偑敽偆丅儃儔儞僥傿傾側偳偱幮夛偲 偮側偑傞偺偲偼暿偺幮夛偺堦堳偱偁傞偲偄偆帺妎傪惗傓丅傑偨丄晇偲懳摍偺娭學偑摼 傜傟傞丅
嘇 廳梫偱偁傞 (僇僫僟彈惈 46%, HIC 35%乯
40戙 丒堚嶻偱傕側偄尷傝丄扤偐偑暥嬪柍偟偵偍嬥傪巊傢偣偰偔傟傞偲偼峫偊偵偔偄丅宱嵪 揑帺棫偼惛恄揑帺棫偲巚偭偰偄傞丅扐偟丄尷傜傟偨廂擖丄傑偨偼偁偊偰廂擖傪彮側偔 偟偰丄帺桼傪帩偮偺傕岾偣偺傂偲偮偩偲巚偭偰偄傞丅
丒廂擖傪摼傞偙偲偵傛傝宱嵪揑偵傕惛恄揑偵傕堦曽揑偵晇傪棅傜側偔偰傕椙偔丄暯摍 側搚戜偺傕偲偵壠掚傪抸偔偙偲偑偱偒傞丅
50戙 丒摥偄偰廂擖偑偁傞偐傜昁偢偟傕岾偣偵側傞偲尵偊傑偣傫偑丄摥偔偲偄偆帠偼惗嶻揑 側偙偲傪偡傞帠傪堄枴偟偰偄傞堊丄偦偙偵帺恎偺枮懌姶偑摼傜傟傞偲巚偄傑偡丅偦傟 偵丄廂擖偑壛枴偝傟傟偽丄帺暘偺岲偒側偙偲傪偡傞斖埻傕峀偑偭偰偒偰岾暉姶傪傕偭 偲帩偪傗偡偄偲巚偄傑偡丅
嘊 偁傑傝廳梫偱偼側偄 (僇僫僟彈惈 26%, HIC 25%乯
30戙 丒崱尰嵼丄梒偄巕嫙2恖傪堢偰偰偄傞偺偱丄堦弿偵偄傠偄傠側強偵楢傟偰偄偭偨傝丄 偍桭払偲梀偽偣偨傝偲偄偆丄巕嫙偵偲偭偰婐偟偄偙偲傗丄偨傔偵側傞偙偲偑岾偣偦偺 傕偺側偺偱丄偨偩丄晇偺棟夝傪摼傜傟側偄応崌丄乬廂擖乭偑側偄偲偄偆偺偑恏偄偲偄 偆偙偲傕偁傝傑偡丅
40戙 丒乽廂擖偵偮側偑傞巇帠傪帩偮偙偲乿僀僐乕儖乽岾偣乿偵偼昁偢偟傕側傜側偄丅壠懓偑 寬峃偱偁傞偙偲丄抧堟偺儃儔儞僥傿傾妶摦偵嶲壛偡傞偙偲丄帺暘偺柌偵岦偐偭偰堦曕 偢偮搘椡偟嬤偯偄偰偄偔偙偲偑岾偣偱偁傞偨傔偺梫慺偩丅
嘋 慡偔廳梫偱側偄(僇僫僟彈惈 4%, HIC 7.5%乯
丒40戙偱偁傞帠丄梒抰墍偵捠偆巕嫙傗妛峑偺庤揱偄摍乆偄傠傫側堄枴偱帪娫傕僄僱儖 僊乕傕廤拞偟偰惗妶偟偰偄傞偙偲丄偦偟偰丄栜榑惗妶偵崲偭偰偄側偄偙偲側偳偐傜乽丒 儏偄偰廂擖傪摼傞偙偲乿偼尰嵼偺巹偑乽岾偣偲姶偠傞乿偙偲偵偼慡偔娭學偁傝傑偣傫丅巕 嫙偑働僈傪偣偢妝偟偔徫偭偰堦擔傪夁偛偟偰偔傟丄傒傫側偑寬峃偱偁傞偙偲丄偙傟偑 傑偢戞堦偱偡丅崱偺偲偙傠岾偣偱偡丅
幙栤俀 巇帠傪帩偮曣恊傕丄巇帠傪帩偨側偄曣恊偲摨偠偔傜偄丄壏偐偔埨掕偟偨娭學傪巕偳傕 偲抸偔偙偲偑弌棃傞丅
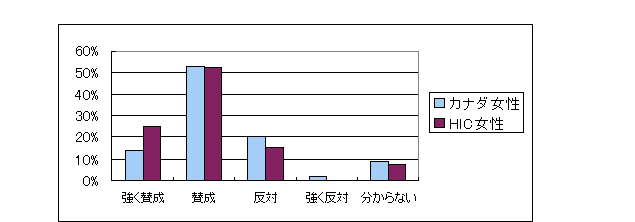
丒恊偑偳傫側偵朲偟偔偰傕丄巕嫙偲偺娫偵嫮偄怣棅娭學傪抸偔偙偲偑弌棃傞偲巚偆丅 傕偪傠傫丄愙偡傞帪娫偑抁偗傟偽丄偦偺暘堄幆偟偰怣棅娭學傪堢偰傞搘椡偑昁梫偩丅 杮摉偵巕嫙偺偙偲傪巚偭偰偄傟偽垽忣偼揱傢傞傕偺偩偲巚偆丅
50戙 丒巹偼曣偑暔怱偮偄偨帪偐傜摥偄偰偄傞惗妶娐嫬偱堢偪丄梒偐偭偨帪偵庘偟偝傪姶偠 偨偙偲偼妎偊偰偄傞偑丄惉挿偡傞偵偟偨偑偭偰巇帠傪偟偰偄傞曣傪偲偰傕屩傝偵巚偭 偨丅恊巕娭學偼枾搙偺栤戣偑廳梫丅
丒巕嫙傊偺垽忣偼検偱側偔幙偱偡丅巕嫙偑擕帣丒梒帣偺帪偼僐儞僗僞儞僩偺曐岇偑戝 愗偱偡偑丄巕嫙偑偁傞擭椷偵払偟偨屻偼丄巕嫙偲愙偟偰偄傞帪庢傞曣恊偺懺搙丒尵摦 偑丄傕偭偲巕嫙払偵塭嬁偡傞偲巚偄傑偡丅偄偮傕巕嫙偑曣恊偐傜垽忣傪庴偗偲偭偰偄 傞偲偄偆妋怣傪梌偊傞偺偵丄偄偮傕傋偭偨傝偡傞昁梫偼偁傝傑偣傫丅
嘇 巀惉 (僇僫僟彈惈 53%, HIC 52.5%乯
40戙 丒帪娫偑惂尷偝傟傞偺偱丄旕忢偵擄偟偄偲偼巚偆偑丄傗偼傝丄偍偺偍偺偺峫偊曽丄惈 奿偵傛傞偲巚偆丅愱嬈庡晈丄偡側傢偪巕嫙偲傛傝傛偄娭學傪抸偗傞丒丒丒偲偄偆帠偵 偼側傜側偄丅
丒帪娫偵惂栺偑偁傞偲丄抦宐傪摥偐偣偰嵟慞傪側偦偆偲搘椡偡傞傛偆偵側傞丅帺桼偵 柍堄幆偵帠偵偁偨偭偰偄傞傛傝丄怱傪偙傔偰廳梫側傕偺偺弴偵傗傠偆偲偡傞偺偱丄嵟 傕戝帠側揰乮曣巕偺娭學側偳乯偼丄儕儈僢僩偺拞偵傕枾搙偺崅偄傕偺偵側傞偺偱偼丅 巕嫙偺曽偵傕桳擄偝偲曣傊偺巚偄傗傝偑堢傑傟傞丅堦惗寽柦偵婃挘偭偰偄傞曣恊偺屻 巔偐傜懡偔偺偙偲傪嫵偊傜傟傞偲怣偠傞丅偦傟偵偼曣恊偺巇帠偵懳偡傞婤慠偲偟偨巔 惃偑栤傢傟傞偺偱偼丅
丒偱偒傞恖偼偨偔偝傫偄傞偩傠偆偟丄惛恄揑偵傕擏懱揑偵傕丄宱嵪揑偵傕梋桾偑偁傟 偽丄廩暘偱偒傞偲巚偆偑丄巹偼惛恄揑偵傾僋僙僋怳傝夞偝傟丄擏懱揑偵偼偄偮傕僿僩 僿僩丄宱嵪揑偵傕傗偭偲壗偲偐傗偭偰偒偨偺偱丄偲偰傕偦偆偄偆娭學傪抸偔偙偲偼偱 偒側偐偭偨偑丄偦傟偼巹偑恖娫揑偵偱偒偰偄側偐偭偨偐傜偩偲巚偆丅
丒巇帠傪帩偨側偔偰壠偵偄偰傕丄昁偢偟傕壏偐偔埨掕偟偨娭學傪抸偔偙偲偼偱偒側偄 丅偦偺斀懳偱丄巇帠傪帩偭偰偄偰傕丄忢偵巕嫙偲偺娭學偵怱傪攝偭偰偄傟偽丄椙偄娭 學傪抸偔偙偲偼壜擻偱偁傞丅曣恊偺恖惗偵懳偡傞惗偒曽偵偐偐傢傞偲巚偆丅
50戙 丒曣恊偑摥偔偲偄偆帠偼丄巕嫙偺柺搢傪傒傞偲偄偆揰偱偳偆偟偰傕庤敳偒偵側偭偰偟 傑偆偲偄偆嵾偺堄幆傪姶偠偨丅偟偐偟丄巕嫙偼恊偺摥偔巔傪尒偰丄壗偐傪妛傇壜擻惈 傕偁傞偺偱偼側偄偐偲巚偭偨傝傕偟偨丅
嘊 斀懳 (僇僫僟彈惈 20%, HIC 15%乯
幙栤俁 巇帠傪帩偮偙偲偼丄彈惈偑撈棫偡傞偨傔偺嵟慞偺曽朄偱偁傞丅
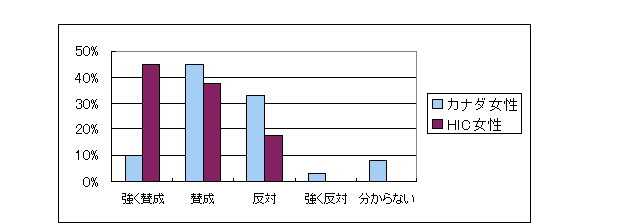
丒彈惈偑撈棫偡傞偨傔偵偼宱嵪揑偵傕惛恄揑偵傕帺棫偡傞偙偲偑昁梫偩丅巇帠傪帩偮 偙偲偼偦偺椉曽傪払惉偡傞偨傔偺嬤摴偩偲巚偆丅幮夛偵弌傞偙偲偱條乆側恖傗條乆側 壙抣娤偵弌夛偄丄帇栰偑峀偑傞丅椙偄惉壥傪摼傛偆偲偟偰丄妛廗偟丄帺暘傪杹偒丄偦 偺夁掱偱嫮偝偲帺怣傪恎偵偮偗偰偄偔丅偦傟偑宱嵪揑側懇敍偲惛恄揑側懇敍傪夝偒曻 偪丄撈棫偟偨恖娫偲側傞偨傔偺嵟慞偺曽朄偩偲巹偼巚偆丅
50戙 丒帺暘偺尰嵼偍偐傟偰偄傞娐嫬偵晄枮傪帩偭偰偄傞恖(彈惈)傕寢嬊偼宱嵪揑側棟桼偱 偦傟偐傜旘傃弌偣側偄偺偑傎偲傫偳偺働乕僗偩偲巚偄傑偡丅偄偮傕帺暘偱帺暘偺恖惗 傪慖戰弌棃傞堊偵丄偦偟偰撈棫偡傞偨傔偵偼宱嵪揑偵堦恖偱傕傗偭偰偄偗傞忬懺丄偮 傑傝廂擖偑偁傞偙偲偑戝慜採偩偲巚偄傑偡丅
丒妋偐偵彈惈偼媼椏偺柺偱偼丄抝惈傛傝偢偭偲掅偄偐傕偟傟側偄偑丄壗偐偁偭偨帪偵 堦恖棫偪偱偒傞偲偄偆偺偼旕忢偵戝愗偱偼側偄偐偲巚偆丅
丒廂擖偑枮懌偺偄偔暘偩偗偁傞偐偳偆偐偼暿偲偟偰丄巇帠傪帩偮偙偲偼惛恄揑側堄枴 偵偍偄偰傕撈棫偡傞偺偵戝愗側帠偱偁傞丅
嘇巀惉 (僇僫僟彈惈 45%, HIC 37.5%乯
丒巇帠傪偡傞偙偲偵傛傝丄宱嵪揑側撈棫傪偼偐傞偙偲偑偱偒丄傑偨楯摥偵傛偭偰幮夛 偵峷專偟偰偄傞偲偄偆帺妎傪帩偮偙偲偑偱偒傞丅
丒宱嵪揑偵撈棫偡傞偨傔偵偼摉慠偺偙偲偩偑丄嫟摥偒偺昁梫偺側偄庡晈偑儃儔儞僥傿 傾妶摦偵娭傢傝丄幮夛偲偺愙揰傪愨偊偢帩偭偰偄傞偺側傜丄斵彈偼廩暘惛恄揑偵撈棫 偟偰偄傞偲尵偊傞偲巚偆丅
50戙 丒巇帠傪帩偮偙偲偼丄壠掚乮晇傗巕嫙乯偲偄偆榞奜偺悽奅偵帺暘傪抲偄偰尒傞偙偲偑 弌棃丄壠偺拞偱偼婥晅偐側偐偭偨壜擻惈傪尒偄弌偟丄枖丄幮夛揑尒幆傕峀偔側偭偰丄 彮側偔偲傕捈愙巇帠傪捠偠偰幮夛偵峷專乮僠儑僢僩丄戝僎僒側尵偄曽偱偡偑乯偟偰偄 傞偲偄偆堄枴偱丄帺棫偟偨乮惛恄柺偱乯暔偺峫偊曽偑弌棃傞偲巚偆丅
嘊 斀懳 (僇僫僟彈惈 33%, HIC 17.5%乯
丒巇帠傪帩偮帩偨側偄偵偐偐傢傜偢丄帺暘偑帺暘偺慖傫偩摴偵枮懌偟偰偄傟偽丄恖娫 偲偟偰嵟慞偱偁傞丅塅栰愮戙偄傢偔乽巹偼寛偟偰巹偺偒傜偄側偙偲偼丄偟側偐偭偨丅 巹偺岲偒側帠偟偐偟側偐偭偨偐傜丄壗傕屻夨偼偟側偄乿丅巹偼偙偺尵梩偑戝岲偒偱偡丅
幙栤係 抝惈丄彈惈偲傕壠寁偺廂擖偵峷專偡傋偒偩丅
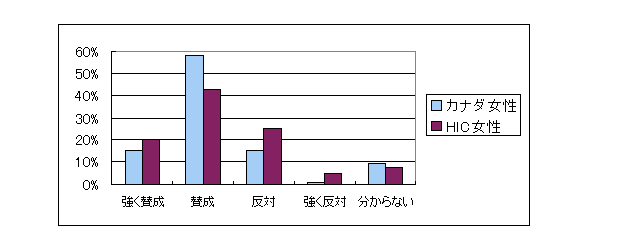
丒偦傟偲嫟偵壠帠傪暘扴偡傋偒丅
50戙 丒摉慠偱偁傞丅偦偺妱崌偑偳偆偐偲偄偆栤戣偼奺壠掚偵傛偭偰堎側傞偲巚偆偑丒丒丒 丅 枖丄帺暘偑梸偟偄暔丄攦偭偨暔傪偄偪偄偪晇偵尵偭偨傝丄抦傜傟偨傝偡傞偺偼姮偊傜 傟側偄丅
嘇 巀惉 (僇僫僟彈惈 58%, HIC 42.5%乯
40戙 丒偦偺帪乆偺忬嫷偵崌傢偣偰丄偦傟偧傟偑弌棃傞斖埻偱丄峷專偡傞偺偑朷傑偟偄丅堦 曽偑昦婥偩偭偨傝丄幐嬈偟偨傝丄妛峑偵捠偭偨傝偡傞娫丄傕偆堦曽偑梋暘偵壠掚傪巟 偊偰峴偗傞傛偆側嫤椡懱惂偑昁梫偩偲巚偆丅傕偪傠傫丄偦偺偨傔偵偼壠帠偲堢帣傪岞 暯偵暘扴偡傞偺偑戝慜採丅
丒抝惈偑傛傎偳偺崅廂擖傪摼偰偄傞応崌傪彍偒丄彈惈傕壠寁偺廂擖偵峷專偟側偄偲丄 埨掕偟偨壠寁傪曐偮偙偲偼擄偟偄帪戙偱偁傞丅傑偨丄僇僫僟偵偍偄偰偼丄忢偵幐嬈偺 嫲晐偵偝傜偝傟丄堦恖偺廂擖偵棅傞偺偼晄埨偱偁傞丅
50戙 丒巕嫙偑彫偝偄帪偼乮摿偵丄壗恖傕偺彫偝偄巕嫙偑偄傞帪偵偼乯丄彈惈偼壠掚偱巕嫙 偺悽榖偡傞曽偑椙偄偲巚偄傑偡丅偲偄偆偺偼丄巕堢偰偼悽奅偱堦斣戝曄側巇帠偩偲巚 偄傑偡偟丄懠恖偼曣恊傎偳擡懴椡偲垽忣偼拲偘側偄偲巚偄傑偡偐傜丅
嘊斀懳 (僇僫僟彈惈 15%, HIC 25%乯
30戙 丒壜擻偱偁傟偽丄壠寁偼抝惈偺廂擖丅彈惈偺廂擖偼偁偔傑偱丄椃峴側偳丄曗彆揑側傕 偺偵巊偆傋偒偩偲巚偆丅
40戙 丒偙傟偼晇晈偺娫偺栤戣偱偁傞丅巹払偼丄崱偼巹偑壱偖帪丄師偼晇偑壱偖帪偲丄暘扴 偟偰偄傞丅 尰嵼偼丄晇偑戝崟拰偱偁傞偑丄10擭屻偼丄巹偑戝崟拰偲側傞梊掕丅
嘋 嫮偔斀懳 (僇僫僟彈惈 1%, HIC 5%乯
幙栤俆 椉恊偑摥偄偰偄傞偲廇妛慜偺帣摱偵椙偔側偄丅
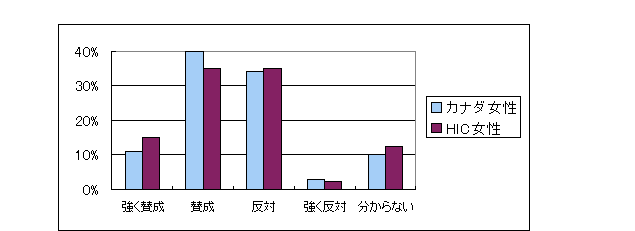
40戙 丒偙傟偵偮偄偰尵偄弌偡偲偒傝偼側偄偑丄廇妛慜偵恊偑庤傪敳偔偲丄偢偭偲巕嫙偺慡 懱揑側恖娫惉挿偵旜傪傂偔丅椉恊偑摥偐偞傞傪摼側偄応崌偼巇曽側偄偑丄帣摱偵椙偔 側偄偙偲偼柧敀偱偁傞丅傂偄偰偼幮夛傕偦傟偵傛偭偰旐奞傪庴偗傞偙偲偵側傞丅
嘇 巀惉 (僇僫僟彈惈 40%, HIC 35%乯
丒偙傟傕椉恊偑乽偳偺偔傜偄摥偄偰偄傞乿偐偵傛傞丅巹偺晇偑丄侾擭偵100擔埲忋奀 奜弌挘丄巹偼巇帠偵擬拞偟偰壠偵偁傑傝婣傜偢丄巕嫙偼儀價乕僔僢僞乕偲儊僀僪偑悽 榖傪偟偰偄偨帪婜偼丄巕嫙偑0嵥乣6嵥敿傑偱偱偁傞偑丄旕忢偵巕嫙偺敪払偵椙偔側偐 偭偨丅傕偪傠傫丄儀價乕僔僢僞乕偼嫵巘偺帒奿偺偁傞曽偱偁偭偨偑丄恊偺戙傢傝偵偼 側傜側偐偭偨丅巕嫙偵偼椙偔側偄偲偼棟夝偟偰偄偨偑丄摉帪偼巹偼乽巕嫙偺柺搢傪尒 傞偙偲乿偵嫽枴偑側偐偭偨偺偱丄偦偆偟偰偄偨丅
50戙 丒廇妛慜偺帣摱偼丄宱嵪揑偵嫋偝傟傞尷傝丄壠掚偱尒庣偭偰傗傝偨偄丅懠恖偵梐偗傞 偺偼曮愇傛傝傕戝愗側傕偺傪摴楬偵傎偭傐傝弌偡傛偆側傕偺丅彮乆偺宱嵪揑媇惖丄僉 儍儕傾偺媇惖偼巕堢偰偺廳梫偝偵偼斾妑偱偒側偄丅
丒巆擮側偑傜偦偆偩偲巚偆丅偑丄偟偐偟丄曣恊偑偦傟傪帺妎偟丄椉恊偑嫤椡偟丄搘椡 偟偰備偗偽丄摥偄偰偄側偄懹懩側曣恊偵堢偰傜傟傞傛傝偼椙偄丅
嘊 斀懳 (僇僫僟彈惈 34%, HIC 35%乯
丒椉恊偺偳偪傜偐偑巕嫙偺嬤偔偵偄偰傗傟傞偙偲偼棟憐偩傠偆偑丄偄偮傕堦弿偵偄側 偔偰傕偦傟偵戙傢傞庤抜偝偊偟偭偐傝偟偰偄傟偽丄巕嫙偼偦傟側傝偵弴墳偡傞偲巚偆 丅傓偟傠懠恖傗懠偺巕嫙偨偪偲愙偡傞偙偲偵傛傝撈棫怱傪梴偆偙偲偵傕側傞丅寢壥揑 偵尒偰丄僨僀働傾偵偄偮傕梐偗傜傟偰偄偨嬤強偺巕嫙偵斾傋丄僫僯乕偲堦弿偵壠偵偄 偨帺暘偺巕嫙偨偪偼偲偭偰傕峫偊曽偑娒偄偲姶偠傞丅嵟嬤丄擔杮偺嫟壱偓偺晇晈偑丄 偍偽偁偪傖傫偵巕嫙傪梐偗偨偨傔丄娒傗偐偝傟偰傢偑傑傑偵堢偪丄妛峑偵峴偒巒傔偰 偄偠傔偺懳徾偵側偭偨偲偄偆榖傪怴暦偱撉傫偱峫偊偝偣傜傟偨傕偺偩丅懠恖傛傝擏恊 偑偄偄偲傕尵偊側偄傛偆偩丅
丒晇偺慡柺揑側嫤椡丄椙偄儀價乕僔僢僞乕傗曐堢強偵宐傑傟偰偄傟偽丄廇妛慜偺帣摱 偵傕埨掕偟偨惗妶娐嫬傪梌偊傞偙偲偼晄壜擻偱偼側偄丅
50戙 丒椉恊偑摥偄偰偄側偄偲帣摱偵椙偄偲丄偄偆媡愢偼惉傝棫偨側偄偲巚偆丅偙傟傜偺栤 戣偼丄椉恊偑摥偄偰偄傛偆偑偄傑偄偑丄偦傟帺懱偁傑傝娭學偑側偄丄偲巚偆丅偦傟傛 傝傕丄偳偺傛偆側恊巕娭學偑庽棫偱偒傞偐偺曽偑栤戣偱廳梫偩偲巚偆丅
丒椉恊偑摥偄偰偄偰傕巕嫙偲偺偮側偑傝傪戝愗偵偟偰偄傟偽丄怱攝偼側偄偲巚偄傑偡 丅懡偔偺帪娫傪堦弿偵夁偛偡偙偲偑堦斣戝愗側帠丅
嘋 嫮偔斀懳 (僇僫僟彈惈 3%, HIC 2.5%乯
嘍 暘偐傜側偄 (僇僫僟彈惈 10%, HIC 12.5%乯
幙栤俇 巇帠傪帩偮偺傕椙偄偑丄彈惈偑杮摉偵朷傫偱偄傞偺偼壠偵偄偰巕嫙傪堢偰傞偙偲偩丅
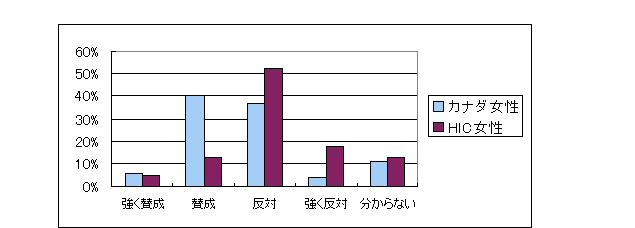
嘇 巀惉 (僇僫僟彈惈 40%, HIC 12.5%乯
嘊 斀懳 (僇僫僟彈惈 37%, HIC 52.5%乯
40戙 丒巕堢偰僆儞儕乕偑惗偒峛斻偲偄偆彈惈傕偄傞偐傕偟傟側偄偑丄巇帠傪偡傞偙偲丄儃 儔儞僥傿傾偵実傢傞偙偲丄幮夛偲偺愙揰傪帩偪懕偗傞偙偲側偳偑昁梫偩偲巚偆丅偦傟 偑彈惈偺岾偣偵宷偑傞偲嫮偔巚偆丅
丒巕嫙偼偄偯傟憙棫偮傕偺偱偁傞丅曣恊傕傗傝偑偄偑偁傞偲偄偆妋怣偺帩偰傞巇帠傪 帩偭偰偄傞応崌丄巕堢偰偲巇帠偺椉棫偼壜擻偱偁傞丅
50戙 丒擻椡丄嵥擻偺偁傞彈惈偼丄巇帠傪帩偮傋偒偩丅
嘋 嫮偔斀懳 (僇僫僟彈惈 4%, HIC 17.5%乯
40戙 丒帺暘偱慖傫偩丄帺暘偺岲偒側摴傪峴偔偙偲丅偦偟偰丄帺暘偺梸偟偄恖乮偮傑傝晇乯 傪惓偟偔慖戰偟庤偵擖傟傞偙偲偑岾偣偱偁傝丄偙偺幙栤帺懱偑巹偵偼慡偔棟夝偱偒側偄丅
50戙 丒抝惈拞怱幮夛偺乬曣惈杮擻恄榖乭偼憗媫偵夵傔偰傎偟偄丅抝偱傕彈偱傕巕堢偰偼廩 暘弌棃傞偺偱偁傞丅 丒傕偪傠傫彈惈偵傛傞偲巚偆丅偟偐偟巕嫙偼昁偢戝偒偔側偭偰恊尦傪棧傟偰偄偔丅偦 偺帪偵丄壠掚偵堦恖庢傝巆偝傟傞彈惈傎偳傒偠傔側傕偺偼側偄丅彈惈亖巕堢偰偺恾幃 偵偼嫮偔斀懳丅傑偨丄旂擏側偙偲偵丄偟偭偐傝偲偟偨巇帠傪偟偰偄傞彈惈傎偳恖娫揑 偵柺敀偄恖偑懡偄丅
嘍 暘偐傜側偄 (僇僫僟彈惈 11%, HIC 12.5%乯
乽彈偺巇帠偼寛偟偰乧乧 偙傟偱傛偟偲偝傟側偄乿
摥偔彈惈偺栶妱偵娭偡傞崱夞偺挷嵏偼丄抝惈偵偼幙栤偟側偄傛偆側偙偲偽偐傝
丂傎偲傫偳偺彈惈偑偦偆偱偁傞傛偆偵丄巹傕挬偼梋暘側帪娫偑偁傑傝側偄丅 丂偱傕丄偁傞擔挬怘傪偲傝丄偍曎摉傪嶌傝丄擇恖偺巕嫙傪妛峑傊憲傝弌偟丄帺暘帺恎 偺僉儍儕傾偱偁傞挊弎嬈傪傗傝偙側偟丄乽傕偟忋偺巕傪崱斢偺偍偗偄偙偵楢傟偰偄偭 偰偔傟偨傜丄巹偼壓偺巕偲棷庣斣偡傞偐傜乿側偳偲枅搙孞傝峀偘傜傟傞晇偲偺妶敪側 岎徛傪偟丄偲偄偭偨挻懡朲側恀偭嵟拞丄巹偼怴暦偺尒弌偟偵揃晅偗偲側偭偰偟傑偭偨丅 亀彈惈偺幮夛揑恑弌偑僇僫僟恖傪崿棎偝偣傞亁 丂巹偼晄埨偵側偭偨丅悽奅偼尰戙彈惈偑壗偨傞偐傪棟夝偟偰偄傞偺偵丄僇僫僟偼崱偩 偵偆傠偨偊偰偄傞傢偗丠 丂偩偑栤戣偼傕偭偲戝偒偐偭偨丅 丂11,000恖偺抝彈傪挷嵏偟偨僇僫僟摑寁嬊偺敪昞偵傛傞偲丄彫偝側巕嫙偑偄傞彈惈偼 壠偵偄傞傋偒偐丄摥偔傋偒偐偲偄偭偨帠偵懳偟偰丄抝彈偲傕乽傗傗柕弬偟偨乿懺搙偑 尒傜傟傞偲偄偆偺偩丅 丂摑寁偱偼彈惈偺51亾丄抝惈偺59亾偑椉恊偑摥偄偰偄傞偲廇妛慜偺巕嫙偵椙偔側偄偲 怣偠偰偄傞丅偦偺堦曽偱丄抝彈偲傕夁敿悢偑丄巇帠偙偦彈惈偑撈棫偡傞偨傔偵偼嵟慞 偺曽朄偱偁傝丄晇傕嵢傕壠寁傪晧扴偡傞傋偒偩偲峫偊偰偄傞丅 丂偙偺柕弬偟偨寢壥偼丄尰戙幮夛偺偹偠傟傞傛偆側嬯摤傪晜偒挙傝偵偟偰偄傞丅偮傑 傝丄壠懓偺梫朷偲巇帠偺梫媮傪偄偐偵偟偰僶儔儞僗傪偲傞偐偲偄偆嬯摤傪偩丅 丂彈惈偨偪偼乽巇帠偼偒偮偄偟丄巕嫙偨偪偺偙偲偑怱攝偩偟丄帺暘偑傗偭偰偄傞偺偼 丄偙傟偱偄偄偺偐傛偔傢偐傜側偄偺丅傕偆旀傟偰媰偒偨偔側偭偰偟傑偆傢乿偲擔忢榖 偟偰偄傞丅 丂傕偪傠傫丄彈惈偨偪偼巇帠偑偆傑偔偄偭偨帪傗堢帣偺婌傃側偳丄惉岟傪岅傝崌偆偙 偲偩偭偰偁傞丅 丂偦傟偵偟偰傕巹偑婥偵擖傜側偄偺偼丄偙偺挷嵏偺巇曽偩丅椺偊偽乽巇帠傪帩偮偺傕 椙偄偑丄彈惈偑杮摉偵朷傫偱偄傞偺偼丄壠偵偄偰巕嫙傪堢偰傞偙偲偩乿偲偄偆傛偆側 幙栤偼丄妋偐偵惓捈側尒夝偱偼偁傞偑丄惈嵎暿揑側尒曽傪偟偰偄傞偐傜偩丅 丂偙偺敀偐崟偐偲偄偆傛偆側幙栤偵偼丄49亾偺抝惈偲41亾偺彈惈偑摨堄傪帵偟偰偄傞 偑丄崱夞偺挷嵏偱偼丄抝惈傪懳徾偵偟偨幙栤偼傂偲偮傕側偄偺偱偁傞丅 丂柧傜偐偵乽彈惈乿偼恖椶偑懚嵼偡傞偙偺抧媴忋偵娷傑傟傞傋偒側偺偵丄彈惈帺恎偵 偝偊偦傟偑尒偊偰偄側偄傜偟偄丅 丂偦偟偰彈惈偼擇幰戰堦偺巚憐偵丄傑偩敍傜傟偰偄傞傛偆偩丅嬥慘偑巹偨偪偺惗妶傪 摦偐偟偰偄傞偙偲傗僼儘僀僩棟榑乮彮側偔偲傕斵偼偙偺揰偱偼惓偟偐偭偨乯乗垽偲楯 摥偑嬒摍偱偁傟偽丄恖偼岾偣偩乗傪柍帇偟偰偄傞丅 丂摥偔曣恊偼16悽婭偺崰偐傜偄偨丅(摥偔曣恊偲偄偆昞尰偼丄偪傚偭偲偍偐偟偄丅傎 偲傫偳偺曣恊偼丄栭柧偗偐傜巕嫙偑栭怮偮偔傑偱偢偭偲摥偒懕偗傞偺偩偐傜丅) 丂偗傟偳傕丄偙傫側偵懡偔偺曣恊偑廇嬈偟偰偄傞偙偲偼丄崱偩偐偭偰側偐偭偨丅尰嵼 丄梒偄巕嫙偺偄傞僇僫僟彈惈偺偆偪丄70亾偑僼儖僞僀儉傑偨偼僷乕僩僞僀儉偱摥偄偰 偄傞丅 丂偁傞幰偼昁梫偵敆傜傟偰丄偁傞幰偼偦偆偟偨偄偐傜丄傑偨偁傞幰偼偦偺椉曽偺棟桼 偱巇帠傪帩偮丅 丂巹偑抦偭偰偄傞岾偣側曣恊偲偼丄巇帠傪帩偪丄側偍偐偮堢帣偵傕廩暘庤傪偐偗傞偙 偲偑偱偒傞彈惈偨偪偱偁傞丅偍偦傜偔斵彈偨偪偼丄枅擔梒偄巕嫙偲夁偛偡偩偗偺屒撈 姶傪杽傔崌傢偣傞偨傔丄僷乕僩僞僀儉偺巇帠偵廇偒丄巕嫙偑偩傫偩傫惉挿偟丄帺棫偡 傞偵偮傟巇帠傪憹傗偟偰偄偭偨偺偩傠偆丅偦偟偰壗傪堦斣偵桪愭偝偣傞傋偒偐 乗 巕嫙偵椙偄僗僞乕僩傪愗傜偣丄恊偲偺愙怗傪曐偪丄埨怱姶傪梌偊傞偲偄偆偙偲傪摢偵 偍偄偰丄巇帠傪寛傔偰偄偭偨丅 丂傕偪傠傫丄偙傟偼宐傑傟偨彈惈偵偟偐偱偒側偄偙偲偱偁傞偑丄崱夞偺挷嵏偱偼偙偺 傛偆側働乕僗偼庢傝忋偘傜傟偰偄側偄丅 丂傕偆傂偲偮挷嵏偑尒摝偟偰偄傞偺偼丄巹偺桭恖偑敳偗栚側偄娤嶡偱摼偨乽椻憼屔偵 怘傋暔偑擖偭偰偄傞偲丄巕嫙偭偰偡偛偔埨怱偡傞偺傛丅偙傟丄巕嫙偺恖惗娤偵娭傢傞 偺傛偹乿偲偄偆帠幚偩丅懡偔偺彈惈偑摥偔棟桼偼丄偢偽傝怘傋傞偨傔偱偁傞丅 丂棟桼偑壗偱偁傟丄摥偔彈惈偼崱夞偺挷嵏偑昞偟偰偄傞埲忋偵丄壠掚傗怑応偱妚柦傪 婲偙偟偰偒偨丅偦偟偰妚柦偼傑偩廔傢偭偰偄側偄丅 丂傑偨丄暿偺懡崙娫儗億乕僩偵傛傞偲丄彈惈偺忋巌偼抝惈偺忋巌傛傝傕偢偭偲僆乕僾 儞偱丄晹壓偵椙偄塭嬁傪梌偊傞偲偄偆寢壥偑弌偰偄傞丅彈惈偼偙偺儗億乕僩傪揧偊偰 棜楌彂傪弌偟偨傝丄僼儗僢僋僗丒僞僀儉惂偲偐丄傕偭偲挿偄嶻媥傗幮撪曐堢強傪梫媮 偟偨傝偡傋偒偐傕偟傟側偄丅 丂偩偑丄擇廳偺栶妱偱儃儘儃儘偵旀傟愗偭偨彈惈憸偺傒偵徟揰傪摉偰懕偗傞尷傝丄偙 偺嬑楯幮夛傪偄偐偵偟偰僼傽儈儕乕丒僼儗儞僪儕乕偵偡傞偐偲偄偭偨摙榑偼榚傊棳偝 傟偰偟傑偆丅偝傜偵丄壠掚撪偱壗傪曄偊偰偄偔傋偒偐偲偄偆媍榑傕棳偝傟偰偟傑偆丅 丂僼僃儈僯僗僩偺戞堦恖幰丄僌儘儕傾丒僗僥僀僱儞偼乽抝偑偱偒傞偙偲偼丄偡傋偰彈 偵傕偱偒傞偲帺妎偡傋偒偩乿偲尵偭偨丅 丂崱丄巹偨偪偼乽彈偑偱偒傞偙偲偼丄抝偵傕偱偒傞偲帺妎偡傋偒乿偱偁傞丅 丂僗僥僀僱儞偼偙偆傕尵偆丅 乽抝偑壠掚偱彈偲暯摍偵摥偔擔偑棃傞傑偱丄彈偼壠偺奜偱抝偲暯摍偵偼側傟側偄偩傠偆乿 丂傕偪傠傫偦偺擔偑棃偨帪丄巹偨偪偼妝墍偱曢傜偟丄傕偆偙傫側挷嵏傪偡傞昁梫偼側 偔側偭偰偄傞偩傠偆偑乧丅
曇 廤 屻 婰
崱夞偺HI夛堳偵懳偡傞傾儞働乕僩挷嵏偺寢壥偼丄摑寁偺朹僌儔僼偱傒傞偲丄HI偺彈 惈偲僇僫僟彈惈偲偺堄幆偺堘偄偼偁傑傝尒傜傟側偐偭偨偲巚偆丅偳偪傜傕丄巇帠傪帩 偮偙偲偲丄巕嫙傪堢偰傞偙偲偺斅偽偝傒偵側偭偰嬯摤偡傞巔偱偁傞丅 偙偺傾儞働乕僩偱嫽枴怺偐偭偨偺偼丄HI僋儔僽儊儞僶乕偺偦傟偧傟偺幙栤偵懳偡傞 僐儊儞僩偑愮嵎枩暿偩偭偨揰偱偁傞丅 巹偼丄懅巕偑惗屻俈儢寧偖傜偄偺帪偐傜懠恖偵梐偗偰丄帺暘偺岲偒側恾彂娰巌彂偺 巇帠傪懕偗偰偄傞丅幙栤俀偺乬摥偔曣恊傕埨掕偟偨壠掚傪抸偔偙偲偑弌棃傞偐乭偲幙 栤俆偺乬嫟摥偒偼廇妛慜偺巕嫙偵傛偔側偄乭偵懳偡傞僐儊儞僩偺拞偵偼丄曣恊晄嵼偑 巕嫙偵媦傏偡塭嬁偵偮偄偰婔偮偐偺斲掕揑側堄尒偑偁偭偨丅尷傜傟偨帪娫偟偐巕嫙偲 夁偛偟偰偄側偄巹偑丄屻傠傔偨偄婥帩偪偵偝偣傜傟偨偙偲偼妋偐偱偁傞丅 偟偐偟丄巕嫙偼曣恊偺垽偩偗偵埶懚偟偰堢偮傕偺偱偼側偄偲巚偆丅 抝偺巕傪夁搙偺曣恊埶懚徢偵偟側偄傛偆堢偰傞偙偲偼丄僞僀儉帍偺婰帠偺拞偱丄僕 儏僨傿僗丒僥傿儉僜儞偑弎傋偰偄傞乽抝偑壠掚偱彈偲暯摍偵摥偔擔偑棃傞偙偲乿偵嬤 偯偔偨傔偺戞堦曕偱偼側偄偩傠偆偐丅
弌嬑慜偺挬乮栭傕偩偗傟偳乯丄怴暦偼尒弌偟偔傜偄偟偐撉傔側偄丅俋寧偺偁傞擔丄 偦偺尒弌偟偺傂偲偮傪尒偨搑抂丄崱擭偺僯儏乕僗儗僞乕偼偙傟偟偐側偄偲巚偭偨丅憗 懍丄曇廤埾堳偺柺乆偵揹榖丅偝偡偑丄僇僫僟摑寁嬊敪昞偵娭偡傞婰帠傪愗傝敳偄偰偄 傞恖偑壗恖傕偄偰丄傗偭偲乮傾僀僨傿傾偑偁傝夁偓乯15廃擭偺僯儏乕僗儗僞乕偺僥乕 儅偼寛傑偭偨丅 帪娫偑嫋偣偽丄20戙偐傜30戙偺曣恊偑傎偲傫偳丄巕堢偰恀偭嵟拞偺乽儅儈乕僘乿偵 傕傾儞働乕僩傪棅傒偨偄強偩偭偨偑丄崱夞偼偙傟偱椙偟偲偟偨偄丅 崱偼擔梛擔偺屵屻俆帪丅崱廡偵尷偭偰巇帠傪壠偵帩偪婣傞僴儊偵側傝丄偝偭偒傗偭 偲偺偙偲偱僐儞僺儏乕僞傪僆僼偵偟偰壓偺僉僢僠儞偵棃偨偲偙傠偩丅乮壗偣嶐栭偼TV 塮夋傪尒偰偟傑偭偨偐傜丅乯傑偢僆乕僽儞偺拞偺價乕僼偺從偗嬶崌傪尒偰丄曇廤屻婰 傪彂偒丄懠偺儊儞僶乕偵揹榖傪偟偰FAX傪憲傝偲偄偆嬶崌丅峫偊偰傒偨傜丄僋儔僽巒 傑偭偰埲棃僘乕僢偲偙傫側挷巕偩丅偍堿偱丄壗搙偍撶傪徟偑偟偨帠傗傜丅偙偺崰偼怘 帠偺屻曅晅偗偑晇偐傜柡払偵戙傢傝丄傑偨乕両側偳偲尵傢傟偰偄傞丅 巹払偺僯儏乕僗儗僞乕偼墂偺傛偆側傕偺丅堦恖傆偲峫偊偨傝丄晇晈傗桭払偲儚僀儚 僀傗偭偨傝丄椃偼備偭偔傝奺墂掆幵偱峴偒偨偄丅偦偺偆偪戝偒側廔拝墂偵拝偄偨傜丄 偦偙偐傜巒敪偵忔傝姺偊偰枖堘偭偨椃傪懕偗偨偄丅
崱夞丄僞僀儉偺東栿傪庴偗帩偭偰傒偰丄昅幰偺堄尒偲帺暘偱峫偊偰偄偨偙偲偑傎偲 傫偳摨偠偩偭偨偺偱丄偲偰傕嫽枴怺偐偭偨丅 巹傕偙偺挷嵏偼丄偁傑傝偵傕昞柺揑偱惈嵎暿揑側幙栤偽偐傝偱丄敀偐崟偐傪栤偄偨 偩偟偰偄傞傛偆偱丄婥偵擖傜側偐偭偨偐傜偩丅 偱傕丄HI僋儔僽儊儞僶乕偺僐儊儞僩偼丄偦傟偧傟屄惈朙偐偱柺敀偐偭偨丅 壠懓丄摿偵擇恖偺巕嫙傪僾儔僀僆儕僥傿乕偵偟偰丄偙傟傑偱巇帠傪挷愡偟偰偒偨巹 偩偑丄傗偼傝晇偺棟夝傗儀價乕僔僢僞乕偵宐傑傟偨偙偲傪姶幱偡傋偒偩傠偆丅 偙傟偐傜傕乮垽偡傞乯僼傽儈儕乕偲乮偁傑傝岲偒偱側偄乯僕儑僽偲乮傎偲傫偳廂擖 偵側傜側偄乯僉儍儕傾偲乮擬怱偡偓傞乯儃儔儞僥傿傾偺僶儔儞僗傪庢傝側偑傜埆愴嬯 摤偟偰偄偙偆両
乽偍椬傝偵庤巻傪帩偭偰峴偭偰偪傚偆偩偄乿偲丄曣偑巻傪偒傟偄偵愜傝偨偨傫偱庤偺 暯偵偺偣偰偔傟傑偡丅偦傟傪戝帠偵帩偭偰峴偔偲丄拞恎傪偪傜傝偲尒偨偍偽偝傫偼乽 傑偁丄偳偆傕偁傝偑偲偆両乿偲丄偍楃偵偍壻巕傪偔傟偰丄傂偲偟偒傝拞偱梀偽偣偰偔 傟傞偺偱偟偨丅 偢偆偭偲屻偱曣偐傜暦偄偨偺偱偡偑丄拞偵偼壗傕彂偄偰側偐偭偨偦偆丅巓偑係嵥丄 巹偑俀嵥丄曣偼嶰恖栚偺弌嶻傪寎偊偰丄偰傫偰偙晳偄偟偰偄偨傛偆偱偡丅敀巻偺庤巻 傪庴偗庢偭偨偍偽偝傫偼丄慺憗偔帠忣傪嶡偟偰丄巹払傪梐偐偭偰偔傟偨偺偱偡丅偦傫 側晽偵巹払偺惉挿偵堦栶攦偭偰偔傟偨椬嬤強偺偍偠偝傫丄偍偽偝傫払偺婄傪巚偄晜偐 傋偰傒傞偲傎偺傏偺偲偟偨婥帩偪偵側傝傑偡丅愻戵婡傕椻憼屔傕揹榖傕側偄帪戙偱偟 偨偑丄偁偺崰偺曽偑帺慠偵嬤偄宍偱傕偭偲恖娫揑偵曢傜偟偰偄偨偺偠傖側偄偐偲巚偄 傑偡丅 崱夞丄傾儞働乕僩偵摎偊側偑傜丄乽彈惈偺幮夛恑弌乿偑壗偐偲榖戣偵側傞埲慜偵巹 払傪堢偰偰偔傟偨曣恊傗偍偽偝傫払偵傕暦偄偰傒偨偄幙栤偩偲巚偄傑偟偨丅
崙嵺寢崶傪偟偨僩儘儞僩嬤峹偺擔杮彈惈偨偪偑廤傑偭偰巒傑偭偨僴乕儌僯乕僀儞僞 乕僫僔儑僫儖僋儔僽傕丄崱偼擔杮岅傪榖偣傞彈惈側傜崙愋丄恖庬偵偙偩傢傜偢扤偱傕 擖傟傞夛偲暆偑峀偔側傝丄偙偺夛偺庡巪偱偁傞堎暥壔娫僐儈儏僯働乕僔儑儞傕廮擃偱 傛傝嫮偔堢偭偰偒傑偟偨丅 崱擭偼15廃擭栚偲偄偆愡栚偱傕偁傝丄擔崰偺妶摦傪椺擭偵傕傑偟偰峀偔擔宯媦傃僇 僫僟幮夛偵岞奐偟丄娨尦偟偨偄傕偺偲巚偄丄惙傝偩偔偝傫側僾儘僕僃僋僩傪慻傒傑偟 偨丅傑偢僗儁僔儍儖僆儕儞僺僢僋傊偺儃儔儞僥傿傾妶摦丄庒偄擔宯偺曣恊偨偪偺乽儅 儈乕僘乿偺夛愝棫傪墖彆丄夛堳娫偺恊杛傪傛傝怺傔傞偨傔偺抋惗夛丄傛傝傾僢僾僨乕 僩側忣曬岎姺偑壜擻側僀儞僞乕僱僢僩揹巕儊乕儖媦傃儂乕儉儁乕僕偺奐愝丄擔杮偐傜 偺廋楙傪嬌傔偨棊岅丒枱嵥偺岞墘傪堏廧幰嫤夛丄怴婇夛偲嫟嵜丄崄峘嵼廧偺僋儔僽憂 棫幰摴抭枩婫巕巵偵傛傞崄峘曉娨偵偮偄偰偺島墘夛丄僋儔僽峆椺偺僺僋僯僢僋丄乽儅 儈乕僘乿偺堏廧幰嫤夛僶乕儀僉儏乕僷乕僥傿傊偺嶲壛丄怴擔宯暥壔夛娰堏揮奼挘巟墖 僠儍儕僥傿乕丒僐儞僒乕僩丄僇僫僟弶偺傾僕傾宯彈惈敾帠偲偟偰僆儞僞儕僆廈朄掛偱 妶桇偝傟偰偄傞擔宯僇僫僟恖丄儅儕僇丒僆儅僣巵偵傛傞島墘丄枅寧堦夞偺儌儈僕僔僯 傾僙儞僞乕傊偺儃儔儞僥傿傾妶摦丄僋儕僗儅僗僷乕僥傿乕丄15廃擭婰擮傾儖僶儉偺嶌 惉丄僯儏乕僗儗僞乕偺敪峴側偳丄偦偺懠偵傕偄傠偄傠夛偲偟偰妶摦偟丄峴帠偵嶲壛偟 傑偟偨丅懡條暥壔幮夛偺僇僫僟偱偙偦丄偙偺傛偆偵曄壔偵晉傓妶摦偑弌棃傞変乆偼旕 忢偵宐傑傟偰偄傞偲巚偄傑偡丅枖怴偟偔抋惗偟偨乽儅儈乕僘乿傪乬怴偟偄慻怐偑怴偟 偄恖払傪擔宯幮夛偵楢傟偰棃偰偔傟偨乭側偳偲懠偺抍懱偺曽乆偑抔偐偔寎偊擖傟偰偔 偩偝偄傑偟偨丅僴乕儌僯乕僀儞僞乕僫僔儑僫儖僋儔僽偼丄偙傟偐傜傕崱傑偱偵傕憹偟 偰偙偺偡偽傜偟偄僇僫僟幮夛偱丄堎暥壔娫僐儈儏僯働乕僔儑儞偺妶摦傪懕偗偰峴偒偨 偄偲巚偄傑偡丅
HARMONYNEWS 丂1996 廐
僴乕儌僯乕丒僀儞僞乕僫僔儑僫儖丒僯儏乕僗儗僞乕 No.17
拞懞儅乕僋乮JFS強挿乯
巹偨偪壠懓偺応崌丄堛幰偐傜偺恌抐傪懸偮傑偱傕偁傝傑偣傫偱偟偨丅晝偑婰壇椡傪娷傔丄惛恄揑偵悐偊偰偄偔偺傪丄巹偨偪偼抦偭偰偄偨偐傜偱偡丅
偟偐偟丄晝偼帺暘偺忈奞傪塀偦偆偲昁巰偱偟偨丅岻傒側幮岎弍偱丄斵偺桭払偼傒側偛傑偐偝傟丄巹偨偪偼姶怱偟偨傎偳偱偡丅晝傪朘栤偟偨桭払偼丄巹偨偪偵偙偆尵偆偺偱偟偨丅 乽偁側偨偺偍晝偝傫偼戝忎晇偱偡傛丅偨偩丄偪傚偭偲朰傟偭傐偔側偭偰偄傞偩偗偱偡傛丅乿
偱傕曣偲巹偼丄晝偑偩傫偩傫偲戅壔偟偰偄偔條巕傪尒偰偄偨偺偱丄傢偐偭偰偄傑偟偨丅晝偑摴偵柪偄巒傔偨崰偐傜丄徢忬偼怺崗偵側傝傑偟偨丅曕偄偰10暘偱栠傞偼偢偑丄20暘丄30暘偲偐偐傝丄偦偟偰50暘傕巔傪尰傢偝偢丄巹偨偪偼怱攝偱偨傑傝傑偣傫偱偟偨丅
傗偑偰丄晝偼壗帪娫傕峴曽晄柧偵側傝丄寈嶡偑斵傪壠偵楢傟栠偟偰偔傟傞帠傕偁傝傑偟偨丅偁偲偐傜巹偨偪偼丄晝偑擔宯嫵夛偺棟帠夛偵峴偔偨傔偵壗帪娫傕抧壓揝偵忔偭偰偄偨傝丄帺戭傪扵偟偰偄偮傑偱傕曕偒夞偭偰偄偨偙偲傪抦傝傑偟偨丅
偟偽傜偔偡傞偲丄晝偼婋尟傪朻偟偰傑偱丄奜弌偡傞帺怣傪側偔偟傑偟偨丅偙偺帪揰偱丄晝偼帺暘偺尷奅傪擣幆偟偰偔傟偨偺偱丄巹偨偪偼傎偭偲偟傑偟偨丅懡偔偺傾儖僣僴僀儅乕昦偺恖偼丄偦偆偄偆偙偲傪擣傔側偄傕偺側偺偱偡丅晝偵埲慜偼昁梫偲偟側偐偭偨僒億乕僩偑偄傞傛偆偵側傝丄傑偨庡偩偭偨晝偺娕岇傪偟偰偄偨曣偵傕僒億乕僩偑昁梫偵側傝傑偟偨丅
傾儖僣僴僀儅乕昦偲偦傟偵偲傕側偆抯曫徢偼丄昦傫偱偄傞摉恖偼傕偲傛傝丄娕岇傪偡傞壠懓偵偲偭偰傕丄幐偆傕偺偑偁傑傝偵傕戝偒偄偺偱偡丅偩傫偩傫偲惛恄偑朻偝傟偰偄偔條巕傪尒傞偺偼丄傓偛偄傕偺偱偡丅昦傫偱偄傞恖偺埿尩傪尒偄偩偡偙偲傕崲擄偱偡丅摿偵偦偺恖偑丄慡偔偺暿恖傊偲曄傢偭偰偄偔傛偆側帪偼丅偟偐偟壠懓娫偱偼丄懜尩偲垽忣偼丄懚嵼偟懕偗傞傕偺偱偡丅
偦傟偱傕娕岇傪偡傞懁偵偼丄嵾埆姶傗搟傝丄梸媮晄枮偺傛偆側斲掕揑側姶忣偑帪乆婲偙傝傑偡丅偩偐傜偙偦丄愑擟偑廳偔尐偵偺偟偐偐傝丄偁傜備傞娕岇傪偟偰偄傞壠懓偵偲偭偰丄僒億乕僩丒僾儘僌儔儉偼婱廳側偺偱偡丅
傾儖僣僴僀儅乕昦偑恑峴偡傞偵廬偄丄偄傠偄傠側寛掕丄帪偵偼偮傜偄偙偲傕寛傔側偗傟偽側傝傑偣傫丅曣偼晝傪偱偒傞偐偓傝壠偱娕岇偟偨偄偲庡挘偟傑偟偨丅偦偙偱巹偨偪偼丄晝偺偨傔偺儂乕儉働傾傗嬤強偺僔僯傾丒僨僀働傾偺僾儘僌儔儉傪棙梡偟傑偟偨丅晝偼偙傟傜傪摿暿婥偵擖偭偰偼偄傑偣傫偱偟偨偑丄曣偵彮偟偱傕帺桼側帪娫傪嶌傞偨傔偵偼丄昁梫晄壜寚偩偭偨偺偱偡丅
偟偐偟丄傗偑偰晝偼塣摦恄宱偑朻偝傟丄曣偼堦擔堦擔偺悽榖偑晄壜擻偵側傝傑偟偨丅傕偼傗巤愝偱偺娕岇傪峫椂偡傋偒側偺偼柧傜偐偱偟偨丅
摑寁忋丄巹偨偪偺庻柦偼挿偔側傝偮偮偁傝傑偡偑丄僇僫僟偵偍偄偰2021擭傑偱偵丄傾儖僣僴僀儅乕昦偺姵幰偼丄尰嵼偺30枩恖偐傜60枩恖偵憹偊傞偲尵傢傟偰偄傑偡丅
巆擮側偑傜傾儖僣僴僀儅乕昦偼丄偙傟偐傜愭傕戝偒側壽戣偲側傞偱偟傚偆丅傑偢丄悽奅拞偵懚嵼偡傞傾儖僣僴僀儅乕昦偺寛掕揑側帯椕朄傪尒偮偗傞偙偲丄偦偟偰丄姵幰偲娕岇偡傞恖払偵偼丄摿岠栻偑尒偮偐傞擔傑偱丄揔愗側僒億乕僩偲僒乕價僗傪採嫙偡傞昁梫偑偁傝傑偡丅
巹偨偪壠懓偼丄晝偺昦忬偑埆壔偡傞偵偮傟丄傑偡傑偡昁梫偲側傞僒億乕僩偲僒乕價僗偵廩暘宐傑傟傑偟偨丅儂乕儉働傾偲僨僀働傾僾儘僌儔儉傪庴偗傞偙偲偑偱偒偨忋丄晝偑幵堉巕傪昁梫偲偟丄嵟屻偵怮偨偒傝偺忬懺偵側偭偨帪丄儌儈僕僿儖僗働傾丒僙儞僞乕偺墖彆偺壓偱丄晝偺暥壔揑僶僢僋僌儔僂儞僪偵崌偭偨僫乕僔儞僌丒儂乕儉偵擖傟傞偙偲偑偱偒偨偺偱偡丅
偟偐偟丄彨棃偼惌晎偑僒乕價僗傪嶍尭偡傞堦曽偱丄偙傟傜偺廀梫偑媡偵懡偔側傝丄姵幰傗娕岇恖偼丄傛傝崲擄側帋楙偵捈柺偡傞偱偟傚偆丅尰嵼偺宐傑傟偨忬懺偑懕偔偲偼尵偊側偄偺偱偡丅
僩儘儞僩偵偁傞傾儖僣僴僀儅乕嫤夛乮TEL 416亅322亅6560乯偼丄巹偨偪偵偄傠偄傠側拤崘偲墖彆傪偟偰偔傟傑偟偨丅妋偐偵昁梫側帪偼棃傞偺偱偡丅彆偗偑梸偟偔偰庤傪嵎偟怢傋傞帪丄彆偗偰偔傟傞桭払偑梸偟偄帪丅偦傫側帪丄傾儖僣僴僀儅乕嫤夛偼怱偺桭偱偟偨丅嫤夛偼揹榖偱偺憡択偵忔傝丄減渏偡傞姵幰傪搊榐偟丄傾儖僣僴僀儅乕昦偺栤戣傪戙曎偟丄懠偺僒乕價僗偺儂僗僩栶偱傕偁傝傑偡丅
傑偨丄嫤夛偼僕儍僷僯乕僘丒僼傽儈儕乕丒僒乕價僗乮JFS乯傗儌儈僕僿儖僗丒僙儞僞乕偺傛偆側擔宯幮夛偺慻怐偲傕丄嫤椡揑偵摥偄偰偄傑偡丅側偤側傜丄傾儖僣僴僀儅乕昦偵娭傢傞姵幰傗壠懓傗桭払偑丄偄偮偱傕僒乕價僗傪庴偗傜傟傞傛偆偵攝椂偟偰偄傞偐傜偱偡丅
傾儖僣僴僀儅乕昦偺偝傜偵徻偟偄忣曬偑梸偟偄曽偼丄擔杮偺乽傏偗榁恖傪偐偐偊傞壠懓偺夛乿[仹802嫗搒巗忋嫗嬫杧愳娵懢挰壓偑傞 嫗搒幮夛暉巸夛娰2奒 戙昞丒崅尒崙惗乮偨偐傒偔偵偍乯TEL075亅811亅8195]傑偱偛楢棈偔偩偝偄丅
(東栿 S.Y.)
(尨暥) Living with Alzheimer's Disease Mark Nakamura Alzheimer's disease is a degenerative brain disorder that destroys vital brain cells. There is no known cause or cure for Alzheimer's disease. It can strike adults at any age, but occurs most commonly in people over 65.
Our family did not have to wait for a diagnosis from a physician. We knew that my father's mental abilities, including his memory, were deteriorating. But he would work so hard at hiding his disability, because he had such excellent social skills, that we marvelled at how well he managed to fool his friends. After visiting him they would say to us, "He's alright. He's just getting a little forgetful.* Except my mother and I knew differently, because we saw the progressive nature of the degeneration.
It first became serious when he started to get lost. At first his disorientation would cause him to turn what might normally be a ten-minute walk, into nerve-wracking twenty, and then thirty, and then fifty-minute disappearances. Eventually, his disappearances would be for many long hours, and we would learn, for example, when the police brought him home, that he had been riding the subway for hours trying to find his way to a meeting of the Christian Fellowship Committee at the Japanese United Church, or that he had been walking for hours looking for his house.
Soon he lost confidence and dared not risk venturing out of the house alone. In that regard we were fortunate because he recognized and accepted his limitations. Many do not. We knew then that he would need additional support he never previously needed nor wanted in his life. And so also would my mother, who was father's primary care-giver.
Alzheimer's disease, and its related dementias take a terrible toll not only on those affected by the disease, but also on their family care-givers. Watching the slow death of the mind is a horrible thing. It is challenging sometimes trying to find the dignity in the person affected by the disease when the person you once knew starts to fade from your view and is replaced by someone else, but the dignity and the love always remain. But there are negative emotions that sometimes remain in the hearts of those who have to care for those affected by the disease, including guilt and anger and frustration. That is why support programs for family care-givers, who must shoulder much of the responsibility and do all of the work, are valuable.
Depending on the nature of the effects of the disease, there are also a range of decisions, hard decisions, that have to be made. My mother insisted on keeping Dad home as long as she could. So our minds turned to providing her with support, including the provision of home care, and local senior's daycare programming for Dad, even though he did not particularly like it. However it was critical to create some free time for her.
But eventually he started to lose his motor control and my mother could no longer manage his day-to-day care. It soon became obvious that we would have to consider some form of institutional care.
Given the demographics, and given the fact that we are living longer, the number of persons affected by Alzheimer's disease in Canada will increase from its current number of 300,000 to 600,000 by the year 2021. Unfortunately, Alzheimer's disease will continue to present major challenges for years to come. First, there is the need to find a cure for a disease that strikes victims universally, throughout the world. Second, we must ensure those affected by the disease, and their care-givers, are provided with the appropriate support and services, until such time as a cure can be found.
Our family was blessed because we were able to access the necessary support and services as the natural progression of the disease increased our need for more and more support. We were able to obtain homecare and daycare programs when we needed them, and we were able to have Dad placed in a culturally appropriate nursing home, under the helping hands of the Momiji Healthcare Society, during his final years, when he was wheelchair and bed-bound.
But the difficulties faced by those affected by the disease may increase, because of government cut-backs to services and increases in demand for them. Nothing should therefore be taken for granted.
We are also fortunate to have organizations like the Alzheimer Society for Metropolitan Toronto (1-416-322-6560) who can provide us with advice and assistance in our time of need. And it is a time of need. It is a time to reach out and seek help. It is a time for finding helpful friends. The Alzheimer Society is a friend. The Alzheimer Society provides Telephone Counseling Services, a Wandering Person's Registry, advocacy on Alzheimer's disease issues and a host of other services. And, it works closely with agencies in the Japanese ethnocultural community, like Japanese Family Services and the Momiji Healthcare Society, because it is committed to providing accessible services to those affected by Alzheimer's disease, and their families and friends.
For additional information on Alzheimer's disease, individuals can also contact the Association of Families Caring for the Demented Elderly Japan. Kunio Takami, Official Staff, Maruta-cho, Sagaru, Horikawa, Kamikyo-ku, Kyoto 802, Japan (075-811-8195)
榁偄備偔恊傊偺憐偄 儌僈乕儖榓巕(HIC夛堳乯 偙偺壞丄俁擭敿傇傝偵椉恊偵夛偄偵婣嫿偟偨丅偲偄偆偺傕丄桭恖偐傜乽擔杮偵堦恖偄傞曣恊偵夛偄偵枅擭婣崙偟偰偄傞抦恖偑丄崱夞婣偭偨傜亀偳側偨條偱偡偐亁偲恞偹傜傟丄幚偺柡傪敾抐偱偒側偔側傞傎偳丄擭榁偄偨恖偺堦擭偼偙傫側偵曄傢傞傕偺偐偲戝僔儑僢僋傪庴偗偨乿偲偄偆榖傪暦偄偨偐傜偱偁傞丅偦傟偵丄傑偩儃働偰偄側偝偦偆側椉恊偲堦弿偵媽杶傪寎偊偨偐偭偨偐傜偱傕偁傞丅
彮側偔偲傕俁擭敿慜偺椉恊偼尦婥偱丄偦傟偧傟偺惗妶偵捛傢傟偐側傝偟傖傫偲偟偰偄偨丅巹偑婣嫿偟偨帪丄86嵨偺晝偼偪傚偆偳攛墛偱擖堾拞偺偨傔昦堾偱夛偭偨偺偩偑丄儀僢僪偺忋偱乽柧擔戅堾偡傞偐傜乿偲帺暘彑庤偵寛傔丄帺戭偱偺傗傝偐偗偺巇帠傪婥偵偟偰偄偨丅壠懓偺傕偺偼丄堦擔偺擖堾旓偺傎偲傫偳偑榁恖堛椕曐尟偱僇僶乕偝傟丄帺屓晧扴偑700墌傎偳側偺偱丄姰帯偡傞傑偱備偭偔傝擖堾偟偰偄偨傜偲尵偆丅偍杶慜偵偼戅堾偱偒偨偑丄晝偼堦夞傝傕擇夞傝傕彫偝偔側偭偰尒偊偨丅偲偙傠偑丄戅堾梻擔偐傜偼挿抝偵忳偭偨揦偺庤揱偄偱丄55cc偺僆乕僩僶僀偵忔偭偰攝払傪偟巒傔奆傪嬃偐偣偨丅
戅堾屻丄俁廡娫栚偵堦捠傝偺専嵏偑偁傞偺偱丄帹偺墦偔側偭偨晝偵偮偄偰昦堾傊峴偭偨丅昦堾偺懸崌幒偼傎偲傫偳榁恖偽偐傝丅乽偳偙傕埆偔側偄傫偩偗偳丄壠偱椻朳偽偐傝偐偗偰傞偲婥寭偹偡偭偐傜丄昦堾偺懸崌幒偵偄偨曽偑椓偟偔偰偄偑偡乿偲偄偆榁恖堛椕偺柍懯巊偄偺偍攌偝傫丅晝偼偲偄偆偲丄攛偺儗儞僩僎儞丄抐柺儗儞僩僎儞丄寣塼専嵏丄僪僋僞乕懸偪偲挬偺俋帪敿偐傜昦堾偵峴偭偰丄廔傢偭偨偺偼俀帪偵嬤偐偭偨丅庒偄恖偑杮摉偵嬶崌偑埆偔偰昦堾偵峴偔偲側傞偲丄堦擔偑偐傝偱媥壣傪庢傜側偗傟偽偄偗側偄埵丄榁恖儁乕僗偱昦堾偑摦偄偰偄傞條偩丅
曣偼偲偄偆偲丄憗挬俆帪敿偵柭傞挰偺僠儍僀儉傛傝傕憗偔丄傑偩敄埫偄係帪敿崰偵婲偒弌偟丄帺暘偺摴妝偱嶌偭偰偄傞栰嵷傗壴敤偵峴偒傂偲巇帠傪偟丄挬怘偺巒傑傞崰偵栠偭偰偔傞丅埲慜偼丄堦椫幵傪巹傛傝憗懌偱僒僢僒僢偲墴偟偰偄偨偺偵丄崱偼堦曕堦曕摜傒偟傔傞傛偆偵曕挷偑抶偔側偭偰偟傑偭偨丅偄傠偄傠側庬椶偺栰嵷傗旤偟偄壴乆偺偁傞搚偄偠傝偺偱偒傞敤偼丄乽巹偺堦斣偺嫃怱抧偺椙偄応強乿偲尵偄愗傞曣偼丄崱偐傜40擭埲忋傕慜偵堛幰偵彆偐傜側偄偲尵傢傟偨娻傪崕暈偟偨婥忎晇側83嵥丅
巹偺屘嫿偼杮摉偵彫偝側挰偱丄傎偲傫偳壠偵尞傕偐偗偢奜弌偱偒傞傎偳婄尒抦傝偽偐傝偺廤傑傝偱偁傞丅偦偟偰丄巹偺幚壠偺傛偆偵慭慶晝曣丄慶晝曣丄庒晇晈丄偦偺巕嫙払偲巐悽戙偑堦偮壆崻偺壓偵曢傜偟偰偄傞壠偑悢審傕偁傞丅妀壠懓偲尵傢傟偰媣偟偄偺偵丄偙偙偼寣偺偮側偑偭偨幰摨巙偟偭偐傝偲寢傃偮偄偰忋庤偔偄偭偰偄傞丅
偄偮偺悽偐傜偦偆寛傑偭偨偺偐抦傜側偄偑丄媨忛導偵偁傞巹偺挰偱偼挿抝偑愓傪宲偓丄傎偲傫偳偡傋偰偺嵿嶻傪憡懕偟丄偦偺戙傢傝偵恊偺巰偸傑偱偺柺搢傪尒傞偲偄傞埫栙偺椆夝偑偁傞丅愭慶戙乆偟偛偔摨慠丄懡悽懷偑傂偲偮偺壆崻偺壓偵曢傜偟偰偒偨偐傜側偺偐傕偟傟側偄丅
媽杶偺8寧13擔偵偼丄曣偺堢偰偨壴傪暓慜偵嫙偊丄愭慶偺偍埵攙傪偙偺擔偺偨傔偵摿暿偵嶌傜傟忺傜傟偨杶扞偵暲傋丄偍婩傝偟丄偦偟偰傑偝偟偔恊巕巐悽戙偦傠偭偰偍曟嶲傝傪偟偨丅偍曟偺拞偵塀傟偰偟傑偭偨屼愭慶條偼丄巕嫙払丄偦偺巕嫙払丄偼偨枖偦偺巕嫙払偵娕庢傜傟丄偍嶲傝偝傟丄偵偓傗偐偱寢峔偩側傫偰埬奜巚偭偰偄傞偺偱偼 乗 丅
乽崱搙偼巹偺斣偩偹乿偲扤偵尵偆偲傕側偔丄曟慜偱偍慄崄傪忋偘傞曣偺庤偼傗傢傜偐偝偺拞偵丄83擭偺曣偺恖惗傪暔岅傞怺偄偟傢偑偄偔偮傕偄偔偮傕廳側偭偰傒偊偨丅
晝偝傫丄曣偝傫丄偁傝偑偲偆丅 婱曽払偺巕偱儂儞僩偵儂儞僩偵椙偐偭偨丅
嶰偮偺僔僯傾丒儂乕儉傪朘偹偰 僒儞僟乕僗媨徏宧巕 (HIC夛堳乯 嵟嬤巇帠偑傜傒偱嶰儢強偺僔僯傾丒儂乕儉傪尒傞婡夛偵宐傑傟偨丅堦偮栚偼擔杮恖偵偼傕偆婛偵偍撻愼傒偺乽儌儈僕丒僔僯傾僙儞僞乕乿(僗僇乕儃儘)偱丄偙偙偼帺暘偺恎偺夞傝偺帠偼帺暘偱弌棃傞偙偲偑擖嫃偺忦審偱偁傞偙偲偼廃抦偺捠傝偱偁傞丅擇偮栚偼堦斒偺僇僫僟恖僔僯傾岦偗偱丄擔忢惗妶偵扤偐偺夘岇偑昁梫側僫乕僔儞僌丒儂乕儉乽儗僇僀丒僙儞僞乕乿(僩儘儞僩)丅偦偟偰嵟屻偼丄偦偺椉曽偺婡擻傪旛偊偨偆偊偵丄榁恖愱栧昦堾傑偱懙偭偰偄傞儐僟儎恖偺偨傔偺乽儀僀僋儗僗僩丒僙儞僞乕乿(僲乕僗儓乕僋)偱偁傞丅
傕偪傠傫擖嫃偟偰傒傟偽丄偳偙傕偦傟側傝偵乽傕偆彮偟偙偆偁偭偰梸偟偄乿偲偄偆僔僯傾偐傜偺梫朷偼偁傞偺偩傠偆偑丄奜偐傜尒妛偟偰榖傪暦偄偨尷傝偱偼丄偦傟偧傟愝旛偑廩幚偟偰偄傞偆偊丄壗傛傝傕庒偄怑堳偨偪偑僥僉僷僉偲摥偄偰偄傞巔偑報徾揑偱偁偭偨丅
乽儌儈僕丒僔僯傾僙儞僞乕乿偵娭偟偰偼丄儃儔儞僥傿傾偦偺懠偱娭傢傝崌偄傪帩偭偰偄傞恖丄傑偨堦搙傗擇搙壗傜偐偺棟桼偱懌傪塣傫偩恖傕懡偄偙偲偲巚偆丅僙儞僞乕偼傑偩弌棃偰巐擭偟偐宱偭偰偄側偄偺偱寶暔帺恎偑怴偟偄帠傕偁傞偑丄壗傛傝擔杮揑暤埻婥傪帩偭偨愝寁偑婐偟偄丅傑偢擖岥傪擖傞偲偡偖偵尒偊傞悈偺棳傟偑恖偺婥帩偪傪儂僢偲偝偣傞偟丄奺庬偺傾僋僥傿價僥傿傪妝偟傔傞拞擇奒偺揤憢傗栘偺彴丄偦偟偰抾偺怉偊崬傒傕丄擔杮偺偳偙偐偱偙傫側僀儞僥儕傾傪尒偨傛偆側婥偵偝偣偰偔傟傞丅惔寜偱偼偁傞偵偟偰傕丄偨偩婡擻堦曈搢偺僾儔僗僠僢僋傗僐儞僋儕乕僩偱偼側偔丄恖娫偺怱傪側偛傑偣傞乽栘乿偑懡偔巊傢傟偰偄傞偺偑丄懠偺僔僯傾丒儂乕儉偱偼梋傝尒偐偗偢抔偐偝傪姶偠傞丅
崱偼擖嫃幰偺20乣25亾偑旕擔宯恖偺嫃廧幰偲偄偆偙偲偩偑丄偣偭偐偔乽擔宯恖丄擔杮恖偺懡偄僔僯傾僙儞僞乕乿偲柫懪偭偰偄傞偺偱丄偄偮傑偱傕偦傟偑懕偔偙偲傪怱傛傝婅偭偰偄傞丅
偦傟偼堦曽偐傜尒傞偲攔懠庡媊偩偲尵傢傟傞嫲傟傕偁傞偑丄怴堏廧幰傗擇丄嶰悽偨偪偑堦惗寽柦廤傔偨婑晅嬥偑丄宱旓偺20亾(屲昐枩僪儖)偵傕払偟偨偙偲傪巚偊偽幐偄偨偔側偄擔宯恖偺巤愝偱偁傞丅
偦傟偵巗撪偵偼拞崙恖丄僀僞儕傾恖丄儐僟儎恖岦偗側偳丄摨偠傛偆側僔僯傾丒儂乕儉傕偁傝丄偦偙傊峴偭偰傒傞偲丄偳偙傕偲偙偲傫僄僗僯僢僋偺暤埻婥偵側偭偰偄傞丅偦偺堦偮偑乽儀僀僋儗僗僩丒僙儞僞乕乿偱偁傞丅
僴僀僂僃乕401偺恀撿偱僶僞乕僗僩捠傝偵偁傞偙偺僙儞僞乕偼丄偦偺婯柾偲偄偄偟偭偐傝偟偨塣塩偲偄偄丄傕偆敿抂偱偼側偄偲偟傒偠傒姶偠偝偣傜傟傞丅
傕偪傠傫恖岥斾偐傜偄偭偨傜丄摉抧偺儐僟儎恖偼擔宯恖側偳栤戣偵偼側傜側偄掱懡偄偐傜偱偼偁傞偑丄擖嫃偟偰偄傞僔僯傾偺壠懓傪儃儔儞僥傿傾偲偟偰僪僢僾儕偲捫偐傜偣丄摿偵僼傽儞僪儗僀僕儞僌側偳偵椡傪擖傟傞偦偺傗傝曽傕幚偵揙掙偟偰偄傞丅
峀戝側搚抧偵僔僯傾丒儂乕儉偐傜巒傑偭偰丄巰偵帄傞傑偱偺偡傋偰偺働傾偑弌棃傞傛偆側愝旛偑惍偊傜傟偰偄傞偑丄乽柍偄偺偼僼儏乕僱儔儖丒儂乕儉偩偗偱偡偹丠乿偲偄偆偲乽偦偺捠傝乿偲偺曉帠偑曉偭偰偔傞偺傪尒偰傕暘偐傞傛偆偵丄偦偙偼儂僗僺僗傑偱懙偭偰偄傞堦戝僙儞僞乕側偺偱偁傞丅
巹偑埬撪偟偨擔杮偐傜偺尒妛幰偑乽榁偄傪寎偊傞晄埨偼偁傝傑偣傫偐丠乿偲儃儔儞僥傿傾偺僣傾乕僈僀僪傪偟偰偄傞丄旘傃愗傝尦婥側榋敧嵨偺彈惈偵暦偄偨傜乽偄偄偊丄偙傟偩偗愝旛偑惍偭偰偄傞偺偱怱攝偡傞帠偼壗傕偁傝傑偣傫乿偲僯僢僐儕偲丄偟偐傕偒偭傁傝尵偭偨偺偑報徾偵巆傞丅
傑偩乽帺戭偺忯偺忋偱巰偵偨偄乿偲偄偆巚偄偺嫮偄偲尵傢傟傞擔杮恖偺丄傑偟偰搶杒抧曽偺彫搒巗偐傜偺尒妛幰偨偪偵偲偭偰偼丄偙偺僙儞僞乕偺梋傝偺揙掙怳傝偵偼嬃偄偨傛偆偩丅
傕偪傠傫偙偙偼丄栧屗偼堦斒偺僇僫僟恖偵傕僆乕僾儞偝傟偰偄傞偲偼偄偊丄怘帠偑儐僟儎恖偺僐乕僔儍乕丒僼乕僪偑庡偲側傟偽丄懠偺僄僗僯僢僋偺僔僯傾偼擖傝偵偔偄偩傠偆丅
嵟屻偺儂乕儉偼僩儘儞僩偺奨拞偵偁傞乽儗僇僀丒僙儞僞乕乿丅偙偙偼偄傢備傞僫乕僔儞僌丒儂乕儉偱偁傞偐傜丄傕偆恎偺夞傝偺偙偲偑帺暘偱弌棃側偔側偭偰偟傑偭偨僔僯傾偨偪偱偁傞偑丄偙偺儂乕儉偺摿挜偼偦傟偙偦僇僫僟偺崙嶔偵傆偝傢偟偔丄27儢崙偺恖偑擖嫃偟偰偄傞偙偲偱偁傞丅偦偟偰偦偺崙乆偺僇儖僠儍乕丒僀儀儞僩傪戝愗偵偟丄枅寧壗傜偐偺僙儗僽儗僀僔儑儞傪峴偆偲偄偆婥偺巊偄傛偆偑傎傎偊傑偟偄丅
弸偄惙傝偺敧寧偵朘偹偨帪偼丄擔杮恖偺擖嫃幰偼偄側偐偭偨偑丄僇僞僐僩偺擔杮岅傪偟傖傋傞娯崙恖偺抝惈偑擖偭偰偄偨丅乽僉儉僠偑怘傋偨偄偑丄恏偄偺偱奝偒崬傫偱偟傑偆偐傜懯栚偩乿偲偄偐偵傕巆擮偦偆偱丄弌棃傟偽偙偭偦傝偲嵎偟擖傟偱傕偟偰忋偘偨偄婥帩偪偵側偭偰偟傑偭偨丅
徚壔偺朩偘偵側傜側偄傛偆偵丄傎偲傫偳偑廮傜偐偔儅僢僔儏偟偨怘傋暔傗棳摦怘偑懡偄傛偆偩偑丄偦傟偝偊傕偆堦恖偱偆傑偔岥偵塣傋偢偵丄庱偵妡偗偨傛偩傟偐偗偑怘傋暔偩傜偗偺僔僯傾偨偪傕懡偔丄偦傫側岝宨傪尒姷傟偰偄側偄幰偵偼捈帇偡傞偺偑恏偄丅
壐傗偐偱怱埨傜偐側榁屻傪憲傝丄偦偺屻偼懠恖偵柪榝傪偐偗側偄巰偵曽傪偟偨偄偲偼扤偱傕偑巚偆偙偲偩傠偆偑丄帺暘偱柦傪抐偨側偄尷傝丄帺暘偺巰傪帺暘偱慖傋側偄恖娫偺廻柦偲偼堦懱壗偐偲丄堦偮堦偮偺応強傪夞傝側偑傜偟偒傝偵峫偊偝偣傜傟偰偟傑偭偨丅
乽亀榁偄亁偼徟傜偢慺捈偵庴偗擖傟偰晅偒崌偭偰峴偔傛傝傎偐偼側偄乿偲偳偙偐偱撉傫偩尵梩偑擼棤傪嬱偗弰傞丅
擔宯擇悽枩嵨両 僐僘儘僽僗僉乕垻晹旤抭巕(HIC夛堳乯 偙偺擭偵側偭偰丄偮偄嵟嬤乽敀榓偊乿偺嶌傝曽傪嫵傢偭偨丅彫偝側偡傝敨偵敀層杻傪擖傟偰偡傝巒傔傞偲僾乕儞偲崄偽偟偄崄傝偑昚偆丅偙傟偵枴慩偲嵒摐傪壛偊偰偡偭偰丄摛晠傪壛偊偰偝傜偵偡偭偰丄浈偱偨僌儕乕儞價乕儞僘傗傾僗僷儔傪寉偔榓偊傞丅偙傫側桪傟偨椏棟朄偑傎偐偵偁傞偩傠偆偐両
巹偺椏棟偺愭惗偼擔宯擇悽偺僩僔偝傫丅彫妛峑偺僶僓乕儖偱旘傇傛偆偵攧傟傞僠儑僐儗乕僩僇僢僾働乕僉丄寛偟偰幐攕偟側偄傾僢僾儖働乕僉丄娙扨偱偍偄偟偄價乕儖捫偗丄偍媞條偵婌偽傟傞僇儕僼僅儖僯傾姫偒丄傔偢傜偟偄昐崌偺壴偲偒偔傜偘偺堦昳乧僩僔偝傫偺偍戭偵偍偠傖傑偡傞搙偵儗僷乕僩儕乕偑憹偊偰峴偔丅揹婥姌傪巊傢偢偵偍偄偟偄偛斞傪悊偔曽朄傕嫵偊偰捀偄偨丅嫮壩偵偐偗偰幭棫偭偰偒偨傜壩傪巭傔傞丅10暘抲偄偰傑偨嫮壩偵偐偗偰悂偄偰偒偨傜壩傪巭傔丄10暘抲偄偰丄偼偄丄偱偒忋偑傝丅愨懳徟偘傞偙偲偑側偄丅侾僀儞僠岤偝偺嶘傪從偔帪偼450搙偺僆乕僽儞偱旂傪忋偵偟偰10暘丄偦偺偁偲僽儘僀儖偱俁暘丅偲偭偰傕崌棟揑丅偐偲巚偆偲丄掚偵怉偊偨偙傫傗偔偄傕偐傜帺壠惢偺偙傫偵傖偔傪偙偟傜偊偨傝丄枴慩傗戲埩傪庤嶌傝偟偰偍傜傟傞丅
乽偄偄曽払偑偦偽偵偄偰埨怱偟偨傢丅乿嶐擭僇僫僟傪朘傟偨曣偑壗搙傕壗搙傕偦偆尵偭偰婣偭偰峴偭偨丅側傫偲変偑壠偺偍岦偐偄偲偦偺擇尙椬偼偳偪傜傕擔宯擇悽偺屼壠掚偱偁傞丅偳偪傜偺屼晇晈傕偍懛偝傫偺偄傜偭偟傖傞擭戙偱桰乆帺揔偺惗妶傪妝偟傫偱偍傜傟傞偺偩偑丄巹偑恎偵愼傒偰岾塣偲姶偠傞偺偼丄偦偺偳偪傜傕戝曄枺椡揑偱恖惗偺偍庤杮偵偟偨偄傎偳慺惏偟偄僇僢僾儖偩偐傜偱偁傞丅
拞偱傕愭弎偺僩僔偝傫偵偼宧暈偡傞偽偐傝丅偍椬偺撈傝廧傑偄偺榁晈恖偺偨傔偵攦偄暔傗嬧峴偵峴偭偰偁偘偨傝丄偄偮傕壗偐偲庤彆偗傪偟偰偄傜偟偨丅偙偺榁晈恖偑僐儞僪儈僯僂儉偵堏偭偰偐傜傕墦偔傑偱壗搙傕懌傪塣傫偱偁傟偙傟柺搢傪尒偰偄傜偭偟傖傞丅偦傟偐傜丄抦傝崌偄偺偍擭婑傝偺捠堾偺憲傝寎偊丄撈傝廧傑偄偺恖偵偼梉怘偵偄傜偭偟傖偄偲婥寉偵惡傪妡偗偰偁偘偨傝丄帺戭偺僉僢僠儞傪夝曻偟偰壗恖傕偺僌儖乕僾偵偍壻巕嶌傝傪嫵偊偰壓偝偭偨傝乧丅偩偐傜僩僔偝傫偺偍戭偵偼幚偵條乆側恖乆偑廤傑偭偰棃傞丅偦偟偰扤偑棃偰傕偄偄傛偆偵偄偮傕怘傋暔偑偄偭傁偄丅巕嫙偺嶶曕偑偰傜棫偪婑偭偨傝偡傞偲丄戝偒側撶偵栰嵷偑偨偭傉傝擖偭偨僗乕僾傪偐偒崿偤偰偄偨傝丄傾僢僾儖僷僀傪偄偭傌傫偵巐偮傕從偄偰偄偨傝偡傞丅儈乕僩僜乕僗傕儔僓乕僯傾傕嶰怘暘丄巐怘暘偨偭傉傝嶌偭偰抧壓偵偁傞嶰戜偺椻搥屔偲擇戜偺椻憼屔偵曐懚偝傟傞丅
変偑壠偵傕偦傫側僩僔偝傫偺偍恖暱偺壎宐偼弔偺塉偺傛偆偵崀傝拲偄偱丄堦岥偵尵偊偽丄傕偆偍悽榖偵側傝偭傁側偟偺忬懺偱偁傞丅擇恖偺懅巕傪傛偔梐偐偭偰壓偝偭偨偺偱丄嶰嵥敿偵側傞師抝偼僩僔偝傫偲偦偺屼庡恖偺僕儑乕僕偝傫乮僩僔偝傫偵晧偗偢楎傜偢偺恖奿幰偱偄傜偭偟傖傞乯傪偮偄嵟嬤傑偱乽偽偁偪傖傫乿乽偠偄偪傖傫乿偲屇傫偱偄偨丅偁傞帪巹偑昦婥偱怮崬傫偱偄傞偲丄巕偳傕偵梉怘傪怘傋偝偣偰偔偩偝偭偨忋偵丄偍姛偵攡姳偟傪揧偊偰撏偗偰偔偩偝偭偨丅僇僫僟惗傑傟偺僩僔偝傫偑嶌偭偰偔偩偝偭偨傑偩搾婥偺偨偭偰偄傞偍姛偵丄巹偼巚偄偑偗側偝偲姶幱偺婥帩偪偱椳偑偁傆傟偦偆偵側偭偨丅
僩僔偝傫傕僕儑乕僕偝傫傕僇僫僟惗傑傟偱丄擔杮偼擇搙嶰搙朘傟偨偙偲偑偁傞偩偗偲偄偆偺偵丄晛捠偺擔杮恖偲嬫暿偑偮偐側偄傎偳擔杮岅偑払幰偱丄擔杮偺揱摑傗峴帠傪傛偔偛懚偠偱偁傞丅偦偟偰擔宯恖偺偳側偨偵傕嫟捠側惤幚偝偲嬑曌偝偵壛偊偰丄恖堦攞偺媊棟偲恖忣傪帩偪崌傢偣偰偍傜傟傞丅崲偭偰偄傞恖偵庤傪嵎偟怢傋傞偙偲偑壗婥側偄擔忢惗妶偺堦晹偵側偭偰偄傞偺偩丅彨棃丄偍嬥偲帪娫偵梋桾偑偱偒偨傜儃儔儞僥傿傾偟傛偆側偳偲峫偊偰偄傞巹偵偼丄栚偐傜偆傠偙偑棊偪傞巚偄偑偡傞丅壓偺巕偑傛偪傛偪曕偒偺崰丄傑偩幵偑堦戜偟偐側偔偰丄偍嶶曕埲奜偼偳偙偵傕峴偗側偄傎偳峴摦斖埻偑嫹偔側偭偰偄偨丅偦傫側帪丄傛偔僩僔偝傫偑擔杮怘昳揦傗拞崙怘昳揦傊偺攦偄暔偵桿偭偰偔偩偝偭偨偺偑戝曄偁傝偑偨偐偭偨丅偦偆偩丄巹傕帺暘偺弌棃傞斖埻偱彫偝側恊愗傪帺暘偺廃傝偺恖偵偟偰偁偘傟偽偄偄偺偩丄偲僩僔偝傫偵弌夛偭偰偐傜婥偑晅偄偨丅
偑丄偦傟傛傝傕壗傛傝傕巹偑偡偛偄偲巚偆偺偼丄擇悽偺曽乆偑偦偆偄偆擔杮恖偑愄偐傜戝帠偵偟偰偒偨旤摽傪偛偔帺慠偵乮偦偟偰墱備偐偟偔乯幚峴偟偰偄傜偭偟傖傞偩偗偱側偔丄偦偺忋偵峏偵僇僫僟恖偺丄偮傑傝杒暷偺丄崌棟惈偲僞僼偝傪寭偹旛偊偰偄傜偭偟傖傞偙偲偩丅
愴慜丄愴拞偲嬯楯傪廳偹側偑傜傕丄師偺悽戙傪棫攈偵堢偰忋偘傜傟偨堦悽偺曽乆偵巹偼怺偄宧堄傪曺偘偨偄偲巚偆丅摨帪偵丄愴憟拞偺偮傜偄懱尡傪忔傝墇偊偰梇乆偟偔塇偽偨偄偰峴偭偨擇悽偺曽乆偵嫮偄姶摦傪妎偊偢偵偄傜傟側偄丅堦恖堦恖偑棫攈偵惗偒傞偙偲偱擔宯恖丄偦偟偰擔杮恖偺抧埵傪崅傔偰壓偝偭偨丅巹偨偪愴屻堏廧幰偼偙偺壎宐偵偳傟傎偳梐偐偭偰偄傞偐寁傝抦傟側偄偲巚偆丅
偙偺擇慻偺慺惏偟偄擇悽僇僢僾儖偲傔偖傝崌偭偨偙偲偱丄巹偺拞偱乽擔宯擇悽亖巗柉偺嬀乿偲偄偆岞幃偑弌棃忋偑偭偨丅偡側傢偪僇僫僟偺擔宯擇悽偲偼擔杮恖偲僇僫僟恖偺嵟傕椙偄強偑愨柇偵儈僢僋僗偝傟偰抋惗偟偨乽棟憐揑側悽戙乿側偺偩偲丅巹偨偪偺巕嫙払傕偙偺傛偆偵堢偭偰傎偟偄偲巚偆丅偦偟偰丄偙偺慺惏偟偄悽戙偺曽乆偲弌夛偄丄偦偺恖惗偵妛傇婡夛傪傕偭偲傕偭偲憹傗偟偰偄偗偨傜偲巚偆丅
乽榁曣傊憲傞柡偺僄乕儖乿 B.H.(HIC夛堳乯 乽巹偑忣偺敄偄曣恊傗偲尵偆偰攷巕偼挿偄偙偲巹傪崷傫偱偹偊丄偁傫偨偨偪偵夛偄偲偆偰傕墦偄偲偙傠偵廧傫偳偭偰傗偟乧乿曣偑巹偺柡偵榖偟偰偄傞偺偑暦偙偊偰巚傢偢僪傾偺奜偵棫偪巭傑偭偰偟傑偭偨丅
乽巹偑惗傑傟傞慜偵晝恊偼愴巰偟偰丄巹偺曣偼恎暘偑掅偄強偐傜壟偄偱偒偨壟傗偲偄偆偰丄幚壠偵栠偝傟偰丄偦傟偭偒傝徚懅傪抐偭偰偟傕偆偨傫偱偡傢乿柡偼弶傔偰暦偔傛偆側傆傝傪偟偰丄乽偍偽偁偪傖傫丄悘暘偮傜偐偭偨偱偟傚偆偹偊乿偲偁偄偢偪傪偆偭偰偄傞丅乽恊偺垽忣傪抦傜傫偲堢偭偨巹偑忣偑敄偄偲尵傢傟偰傕乧乿偲傔偳側偔曣偼媣偟傇傝偵夛偭偨懛柡偵娒偊偰慽偊偰偄傞傛偆偩偭偨丅
柧帯34擭俁寧惗傑傟丄乮徍榓揤峜偲摨偄擭丄偲偄偆偺偑壗屘偐曣偺帺枬偱偁傞傜偟偐偭偨乯摉擭偲偭偰95嵥偲俈僇寧丅柧帯丄戝惓丄徍榓偦偟偰暯惉偺悽傕俉擭偲側偭偰傕惗偒側偑傜偊偰偄傞丅朙壀丄恄屗偱偼悈奞偱壠傪幐偄丄愴憟偱擇搙從偗弌偝傟丄偦偟偰傑偨愭擭偺嶃恄戝恔嵭偵傛偭偰丄曣偺廔偺廧傒偐偱偁偭偨恄屗偺壠偼慡夡丄柦偐傜偑傜扥攇偺榁恖儂乕儉偵旔擄偟偨丅
曣偑崱廧傫偱偄傞偦偺儂乕儉偼扥攇偺幝嶳偲偄偆強偵偁傞丅扥攇偺揷幧偲偄偭偰傕崱擭偺俇寧偵暋慄偵側偭偨偺偱戝嶃偐傜摿媫偱侾帪娫庛偱峴偗傞丅偙偺弶廐偵偼偪傚偆偳墿嬥怓偺堫曚偑廳偨偘偵悅傟壓偑傝丄偨偭傉傝偲恎偺擖偭偨巬摛偑斵娸壴偺嶇偒棎傟傞偁偤摴偵柍憿嶌偵搳偘弌偝傟偰偄傞丄徏戼傗戝偒側戝偒側偔傝偑嵦傟傞嶳娫偵偁傞儂乕儉偺掚偺堉巕偵崢傪妡偗偨曣偼乽偙偙偼傎傫偵偊偊偲偙偱偡乿偲尵偆丅60擭梋傝傕搒夛曢傜偟傪偟偨恖偲偼巚偊側偄傎偳丄曣偺巔偼偦偺嫿廌傪偦偦傞宨怓偺拞偵偟偭偔傝偲廂傑偭偰偄傞丅
曣偺夘岇偑弌棃側偄丄乮慜弎偺傛偆偵壗偲尵偭偰傕偙偪傜偵偼棃偰偔傟側偐偭偨乯巹偺偣傔偰傕偺嵾柵傏偟偺偮傕傝偱巒傔偨擔宯榁恖偺偨傔偺儃儔儞僥傿傾妶摦傕嵶乆偱偼偁傞偑崱擭偱俈擭偵側傞丅僌儕乕儞價儏乕丄儌儈僕偺90嵥埲忋偺曽乮庡偵彈惈乯偵偼摿暿偺巚偄傪婑偣偰偄傞丅偙偺曽乆堦恖堦恖偑曣偲摨偠偔偁傝偲偁傜備傞帋楙傪宱偰塩乆偲惗偒懕偗偰偙傜傟偨丄偦偟偰尰嵼偼斾妑揑壐傗偐側榁偄偺擔乆傪夁偛偟偰偍傜傟傞丅曣偲摨偠傛偆偵偐側傝栠偭偰偄傞恖傕偄傜偭偟傖傞傕偺偺丄乮曣偺応崌偼傑偩傜儃働丄彑庤儃働 乗 搒崌偺埆偄偙偲偼朰傟傞乯尪妎徢忬丄減渏丄恖奿寚懝偦偟偰怮偨偒傝丄偙偆偟偨斶嶴偱愨朷揑側忬懺偱側偄偺偼媬傢傟傞巚偄偑偡傞丅
乽恖娫偼摢傕懱傕摦偐偟偰偨傜懝乮偄偨乯傓偺偑抶偄偲巚偄傑偡乧乿曣偼孼偑朣偔側傞偪傚偭偲慜傑偱壠帠傪偙側偟偰偄偨丄偦偺偙傠傕偆90嵥傪墇偊傛偆偲偟偰偄偨傠偆偐丄崱傗擔栭擡傃婑傞榁偄偺塭偵偍傃偊偰丄庒曉傝偵晠怱偡傞偽偐傝偱偁傑傝摢傕懱傕摦偐偟偰偄傞偲偼尵偊側偄巹偵偲偭偰丄偙偺帄尵偙偦偑曣偐傜巹傊偺憽傝暔偲巚傢偹偽側傜側偄偩傠偆丅
偙偺俁寧旾傪暋嶨崪愜偟偰丄堛巘偐傜嫮偔庤弍傪姪傔傜傟偨偵傕峉傢傜偢丄抐屌抐傢傝丄偡偭偐傝帺椡偱帯桙偝偣偰偟傑偭偨丄傢偑曣偼恀偵寬嵼偱偁傞丅乽晝傗孼偵嬯楯偽偐傝偝偣傜傟偰丄壗堦偮偤偄偨偔傕偟側偄偱壗偑妝偟傒偱惗偒偰偄傞偺乿偲偄偮傕曣傪垼傟傫偱偄偨巹偱偁傞偑丄崱偲側偭偰偼偙偺嫮恱側嵃傪帩偮嵟屻偺柧帯偺恖偵扙朮偟偰丄乽偍曣偝傫丄偟偭偐傝両乧偙偆側偭偨傜愨懳偵堦悽婭傪墇偊偰傕惗偒偰偹乿偲僄乕儖傪憲傝懕偗傛偆偲巚偆丅
恊岶峴丄僇僫僟斉 S.H.(HIC夛堳乯 愄偐傜恊岶峴偟偨偄帪偵偼恊偼側偟 乗 偲尵傢傟傞偑丄偨偲偊恊偼寬嵼偱傕墦偔棧傟偰廧傫偱偄偰偼擔忢儗儀儖偱偺嵶偐偄悽榖偼偱偒側偄棫応偺巹払偵偲偭偰丄師偵偛徯夘偡傞偍榖偼慉傑偟偄傛偆側忦審偵宐傑傟偰偄傞偲巚偊傞偐傕偟傟傑偣傫丅偟偐偟彮偟偱傕偳側偨偐偺偛嶲峫偵側傟偽偲彂偄偰傒傑偟偨丅
僩儘儞僩巗撪偵廧傓俲巵偼丄擇擭慜偵晝恊傪朣偔偝傟丄尰嵼84嵨偵側傞堦恖廧傑偄偺曣恊偺偍悽榖傪偟偰偍傜傟傞丅晝恊偑朣偔側傜傟傞慜偺屲擭娫偼栍栚偺晄帺桼傪宱尡丅偦偺娫丄娕昦偡傞曣恊偵偐偐傞偛晧扴偼戝曄側傕偺偩偭偨偲憐憸偡傞丅榁悐偱晝恊傪朣偔偝傟偨堦擭屻偵丄崱搙偼曣恊偺枀偵偁偨傞廸曣傪僈儞偱朣偔偝傟偨丅俲巵偼巕嫙偺側偄廸曣偺偨傔丄昦堾偺憲寎偼傕偲傛傝丄僴僂僗僉乕僷乕丄僫乕僗朘栤偺庤攝丄朣偔側傞捈慜偼曣恊偺壠偵楢傟偰婣傝帺戭娕岇丅榁恖偵偼乬昦堾乭偺娐嫬傪寵偆恖偑懡偄丅岾偄傑偩尦婥側曣恊偲廡嶰丄巐夞偺僴僂僗僉乕僷乕丄僫乕僗朘栤偱庤岤偔娕岇偝傟丄昦婥敪尒偐傜敧儢寧屻偵廸曣傪娕庢傜傟偨丅偦偺屻丄84嵨偵側傞曣恊偺婥棊偪偑寖偟偔丄巵偼堦儢寧掱偼曣恊偲惗妶傪嫟偵偝傟偨丅
偦偺屻傕擔傪寛傔偰儅乕働僢僩丄嬧峴丄旤梕堾側偳偺憲傝寎偊傪懕偗偰偍傜傟傞丅廡枛偵偼塮夋岲偒偺斵彈偺偨傔偵堦廡娫暘偺僉儍僾僔儑儞晅偒價僨僆傪庁傝偨傝丄嬤偔偺恾彂娰偐傜戝偒側暥帤偺杮傪庁傝偰偒偰偼堦恖廧傑偄偺曣恊傪堅傔偰偍傜傟傞丅壠拞偺揹婥惢昳偼巊偄堈偄傛偆偵戝偒偔娙扨偵昞帵丄彴偵偼抜嵎偑側偄傛偆偵丄枖偼僇乕儁僢僩傗揹婥僐乕僪偱偮傑偢偐側偄傛偆偵丄帄傞強偵岺晇偑側偝傟婥攝傝偑桪偟偄丅
婥暘揮姺偵偲丄愜傝偵傆傟偰嶶曕偵丄僪儔僀僽偵偲楢傟弌偡丅僶儔偺嶇偔崰偼偙偺岞墍丄屛偺撯偄偩擔偼價乕僠偵偲丅廧傒姷傟偨嬤強傪嶶曕偡傞偩偗偺曣恊偵偲偭偰偼愄榖偑恠偒側偄偦偆偩丅妋偐偵俲巵偺応崌丄幵偱悢暘偲偄偆嫍棧丄斾妑揑帪娫偑帺桼偵側傞怑嬈丄宐傑傟偨宱嵪帠忣偲慉傑偟偄傛偆側忦審偑旛傢偭偰偄傞丅偟偐偟丄巵偑堦斣怱偑偗偰偄傞偙偲偼丄嬤擭偲傒偵帹偺晄帺桼側曣恊偲偺僗僉儞僔僢僾偩偦偆偩丅梒偄巕偲偺僗僉儞僔僢僾偺廳梫偝偼彞偊傜傟偰媣偟偄偑丄榁偄備偔恊偲偺僗僉儞僔僢僾偺戝愗偝偼偁傑傝暦偐側偄丅偦偟偰偳傫側偵嵄嵶側偙偲偱傕丄塡榖偱傕帹傪孹偗傞偙偲偩偦偆偩丅僼儞僼儞偲偆側偢偔偩偗偱傕傛偄丅戝掞偺応崌丄帹偺墦偄榁恖偲偺夛榖偼堦曽捠峴偺応崌偑懡偄偺偩偐傜丅巹払擔杮恖偵偲偭偰偼丄hug偟偨傝偡傞偙偲偼婥抪偢偐偟偄偙偲偱偁傞偑丄偦偭偲尐偵庤傪抲偄偨傝丄攚傪巟偊偨傝丄傎傫偺彮偟偺怗傟崌偄偱傕傛偄丅庩偵抝惈彅巵偵偼徠傟廘偄偙偲偐傕偟傟側偄偑 乗 丅
擔杮偲僇僫僟偱偼僗僉儞僔僢僾傕傑傑側傜側偄栿偱丄梄曋丄揹榖偺庤抜偵棅傞懠側偄丅僇乕僪傪憲偭偨傝丄抁偔偰傕夞悢傪懡偔偡傞偙偲偑戝愗偩偲巚偆丅偛椉恊偑僇僫僟偵廧傫偱偄傞恖偺応崌丄嵟婑傝偺巗偺學偲楢棈傪枾偵偟偰丄柍椏傑偨偼妱埨偺僒乕價僗傪棙梡偡傞偙偲傪偍偡偡傔偟偨偄丅俲巵偄傢偔丄帺暘偺曣恊偩偐傜嵢偵晧扴傪偐偗傞傛傝丄弌棃傞尷傝帺暘偱悽榖傪偟偨偄 乗 偲丅
曇廤屻婰
嵟嬤丄桭恖偲偺夛榖偵巕嫙偺帠傛傝傕丄傛偔恊偺榖偑弌偰偔傞偺傪姶偠傑偡丅僴乕儌僯乕丒僀儞僞乕僫僔儑僫儖丒僋儔僽(HIC)偺夛堳偺傎偲傫偳偼巕堢偰傕恑峴拞側偺偱偡偑丄偐偮偰帺暘傪堢偰偰偔傟偨恊偑抜乆扤偐偺庤彆偗傪昁梫偲偟偰棃偰偄傞偺傪傂偟傂偟偲姶偠偰傕偄傑偡丅恊偱偁傟扤偱偁傟丄惛堦攖恖惗傪曕傫偱偒偨愭恖偺曽払偵偼丄彮偟偱傕怱朙偐側崅楊婜傪憲偭偰梸偟偄丅偦傫側憐偄傪崬傔偰丄崱擭偺僯儏乕僗儗僞乕偼乽榁偄備偔恊傊偺憐偄乿偲寛傔丄媣偟傇傝偱夛堳偺尨峞傪拞怱偵曇廤偟偰傒傑偟偨丅
傂偄偰偼帺暘傕宱尡偡傞崅楊婜偵偼丄乽宱嵪丄寬峃丄惗偒偑偄丄偦偟偰忣曬乿偑昁梫偲尵傢傟傑偡丅傾儖僣僴僀儅乕昦偵滊偭偨偍晝條偲偛壠懓偺巔傪丄尰嵼偺僩儘儞僩偺暉巸丒峴惌偲嫟偵偛徯夘捀偄偨拞懞儅乕僋偝傫丄扺乆偲偟偨拞偵姶摦偡傜妎偊傑偟偨丅屼婑峞丄杮摉偵偁傝偑偲偆偛偞偄傑偟偨丅傑偨丄婎杮揑側僩儘儞僩偺忣曬偲偟偰丄僼儕乕儔儞僗丒僕儍乕僫儕僗僩偱HIC夛堳偱偁傞僒儞僟乕僗媨徏宧巕偝傫偺乽嶰偮偺僔僯傾丒儂乕儉傪朘偹偰乿偼戝曄嶲峫偵側傞偲巚偄傑偡丅尨峞偵丄東栿偵丄曇廤偵丄峀崘廤傔偵丄撉傒崌傢偣偵丄偲崱擭傕懡偔偺夛堳偺暠摤偑偁偭偰僯儏乕僗儗僞乕偑弌棃忋偑傝傑偟偨丅奆條偁傝偑偲偆偛偞偄傑偟偨丅偍堿條偱丄曐懚斉偲尵偊傞傎偳偺撪梕偵側傝傑偟偨丅枅擭丄婥帩偪椙偔峀崘傪壓偝傞曽乆偵傕丄夵傔偰怺偔姶幱怽偟忋偘傑偡丅
HIC傕擭傪廳偹丄棃擭偼15廃擭偵側傝傑偡丅妛惗偺僋儔僽偱偼丄偲偰傕偙傫側偵挿偔偼妶摦偱偒側偄偱偟傚偆偑丄偄偮偺娫偵偐巹偨偪傕僩僔傪庢偭偰偒偰偄傞栿偱偡偹丅偱傕丄偙偺娫丄堦悽僨乕偱偍栚偵偐偐偭偨103嵥偺曽偵斾傋偨傜丄傑偩傑偩乬庒攜乭丅偙傟偐傜傕媂偟偔偍婅偄抳偟傑乣偡両
彯丄崱擭偺廐丄HIC偼儘僀儎儖僆儞僞儕僆攷暔娰偺擔杮僐儗僋僔儑儞扴摉幰丄僸儏乕丒儚僀儕乕攷巑偺僗儔僀僪偲島墘乬擔杮偲巹偺岾塣側弌夛偄 '63乭傪峴側偄傑偟偨丅嶲壛幰偼戞堦尵岅偑塸岅偺曽丄擔杮岅偺曽敿乆偱丄島墘屻傕榓婥偁偄偁偄偲岎棳傪妝偟傒傑偟偨丅
偁偭偲偄偆娫偵傕偆擭偺悾偱偡丅 奆條丄偳偆偧傛偄僋儕僗儅僗偲怴擭傪偍寎偊壓偝偄丅 僴乕儌僯乕丒僀儞僞乕僫僔儑僫儖丒僋儔僽夛挿 僋儕僾僔儍儉惏峕